葬儀後にやるべきことは?法要から相続手続きまで徹底解説

葬儀を終え、一息ついたのもつかの間。悲しみの中、残されたご家族には多くの手続きが待ち受けています。何から手をつければいいのか、誰に相談すればいいのかわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、葬儀後にやるべきことを4つのカテゴリーに分けて、手続きの内容や期限、注意すべきポイントを解説します。やるべきことの全体像を把握し、ひとつずつ着実に進めていくための道しるべとして、ぜひお役立てください。
葬儀後にやるべきことの種類
葬儀後はやるべきことが山積みです。限られた時間の中で優先順位がつけるのが難しい方や、そもそも何をやらなければいけないか整理できないという方も多いでしょう。
本記事では、やるべきことを大きく4つに分類して整理します。
1つ目は、主に役所でおこなう公的な手続きです。故人が受け取っていた公的年金や健康保険の手続きなど、期限が設けられているものもあるため、できるだけ早めに対応する必要があります。
2つ目は、電気やガス、携帯電話といった身の回りの契約の解約・名義変更など、相続手続きが完了する前におこなえる手続きです。
3つ目は、仏壇や位牌、四十九日法要など、故人の供養に関することです。葬儀で親族が集まった際に決めてしまう場合もありますが、喪主が主体となって手配しなければならない場合もあります。
4つ目は、相続手続きです。故人の財産を誰がどのように受け継ぐのか、円満に話し合いを進めることが大切です。
やるべきことを整理した上で、必要に応じて親族や専門家の力を借りながら、ひとつずつ対応していきましょう。以下では、4つの分類ごとに具体的な手続きを解説していきます。
葬儀後に役所でおこなう手続き
年金や保険関連の手続きには、比較的短い期限が定められているものが多いのが実情です。手続きが遅れると、思わぬ不利益が生じることもあります。一つひとつ、心を落ち着けて確認していきましょう。
公的年金受給停止
故人が公的年金を受給していた場合、年金の種類にかかわらず受給停止の手続きをおこないます。年金を受けとる前の年齢だった場合や、年金を受給していなかった場合は不要です。
国民年金や厚生年金の場合は年金事務所または故人の住所地の市区町村役場、共済年金の場合は各共済組合で手続きをおこないます。期限は、国民年金・厚生年金が亡くなった日から14日以内、共済年金が1ヶ月以内です。
故人のマイナンバーが日本年金機構に登録されていれば、市区町村役場に死亡届を提出すると、その情報が年金機構にも通知されるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出は原則として省略できます。ただし、遺族が受け取れる未支給年金がある場合は、別途請求手続きが必要です。
必要書類の例
- 年金受給権者死亡届
- 故人の年金手帳
- 死亡診断書(死体検案書)のコピーまたは住民票除票
- 故人と手続きをおこなう方の関係がわかる戸籍謄本など
健康保険の資格喪失届
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、故人の住所地の市区町村役場に資格喪失届を提出します。会社の健康保険の場合は勤務先での手続きが必要です。期限は原則として亡くなった日から14日以内です。
マイナンバーカードは死亡届を提出すると自動的に失効しますが、健康保険や介護保険の資格は自動的に喪失するわけではありません。また、従来の保険証を利用している場合は保険証の返却も必要です。
必要書類の例
- 健康保険資格喪失届
- 故人の保険証
- 死亡診断書(死体検案書)のコピーまたは住民票除票
- 手続きをおこなう方の本人確認書類
介護保険の資格喪失届
故人が65歳以上で介護保険被保険者証をもっていた場合、故人の住所地の市区町村役場の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。
こちらも原則として亡くなった日から14日以内です。手続きを怠ると、保険料の請求が続くなど思わぬトラブルにつながる可能性があるため、忘れずにおこないましょう。
必要書類の例
- 故人の介護保険被保険者証
- 手続きをおこなう方の本人確認書類
住民票の世帯主変更
故人が世帯主でほかに同じ世帯に残る方がいる場合、住所地の市区町村役場で手続きが必要です。故人が世帯主ではなかった場合や、世帯で唯一の方だった場合は不要です。
期限は原則として亡くなった日から14日以内です。死亡届の提出時に同時に済ませている場合もあります。
必要書類の例
- 住民異動届
- 手続きをおこなう方の本人確認書類
雇用保険受給資格者証の返還
故人が失業保険を受給していた場合、受給権が消滅するため手続きが必要です。手続きは故人が失業保険の手続きをしていたハローワークでおこないます。特に厳密な期限はありませんが、なるべく早く返還しましょう。
必要書類の例
- 雇用保険受給資格者証
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー
相続手続き前にできる解約・名義変更手続き
相続手続きが完了するまでは、故人名義の契約や財産には手をつけないのが原則です。しかし、電気やガスといったライフラインや携帯電話は、亡くなったあとも費用が発生し続けます。
これらの契約は、相続財産とは別物と考えられるため、相続手続きを待たずに解約や名義変更をしても問題ない場合がほとんどです。
公共料金(電気、ガス、水道)
故人が契約していた公共料金(電気、ガス、水道)の名義変更や解約は、早めにおこなうことをおすすめします。契約会社によって手続き方法は異なりますが、多くの場合、電話やインターネットで名義変更や解約が可能です。
引き続き故人の住居に住む方がいる場合は、名義変更手続きをおこないます。一方、故人の住居を引き払う場合や空き家になるためライフラインを必要としない場合は、解約手続きをおこないましょう。
手続きをスムーズに進めるために、公共料金の請求書や検針票に記載されているお客様番号や契約者情報などを手元に用意しておくと便利です。
必要書類の例
- 手続きをおこなう方の本人確認書類
- 故人の死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)
- 故人の住民票除票
- 公共料金の請求書
携帯電話・インターネット回線
故人が契約していた携帯電話やインターネット回線も、早めに解約または名義変更の手続きをおこないましょう。契約している通信会社に連絡して手続き方法を確認します。
必要書類(物品)の例
- 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本など)
- 手続きをおこなう方の本人確認書類
- 故人の携帯電話・SIMカード
- 故人の契約情報がわかる書類(請求書、契約書など)
【注意】相続手続きが終わるまでには遺産に手をつけない
相続手続きを進める上で、故人の財産(遺産)には安易に手をつけてはいけません。
故人が残された預貯金から葬儀費用を支払うことはできますが、その場合でも領収書を保管するなど、何にいくら使ったかを明確にしておく必要があります。これは、後々の遺産分割協議や相続税申告の際に必要となるためです。
故人の預貯金から勝手に引き出して使ってしまうと、相続を「単純承認」したとみなされ、故人の借金や負債も全て引き継ぐことになってしまう可能性があります。特に、故人に借金があったかもしれない場合は、安易に遺産を処分したり、使ったりしないよう十分注意しましょう。
葬儀後の法要や供養
葬儀が終わり、故人を偲ぶための法要や供養もおこないます。これらは、故人の冥福を祈り、ご遺族の気持ちを整理する上で大切な時間です。宗教や宗派によって法要の時期や内容は異なりますが、ここでは仏教の一般的な流れを紹介します。
葬儀費用を支払う
葬儀を終えると、葬儀社や寺院、火葬場などから請求書が届きます。請求書の内容をひとつずつ確認し、速やかに支払いを済ませましょう。葬儀費用は、故人の預金から支払うことが認められています。
ただし、後々のトラブルを避けるために、故人の預金からいつ・いくら引き出して何に使ったのかを明確にし、請求書や領収書を保管することが重要です。これらの書類が遺産分割協議や相続税の申告の際に必要となる大切な証拠になります。
故人の借金が多そうな場合でも、葬儀費用を支払っただけであれば、相続放棄ができなくなる「単純承認」にはあたらないとされています。

香典返しを贈る
香典返しは、葬儀に参列し香典をいただいた方々へ、感謝の気持ちを伝えるためのものです。一般的には、いただいた香典の金額の半額から3分の1程度を目安に品物を選びます。
香典返しの品物は、不幸をあとに残さないという意味合いから、食べ物や消耗品など「消えもの」が選ばれることが多いです。
贈るタイミングは、四十九日法要を終えたあとが一般的です。のし紙には「満中陰志」などの表書きをつけ、贈り主(喪主)の名前を入れます。最近では、葬儀当日に香典返しを済ませる「当日返し」を選ぶ方も増えています。
仏壇や位牌を手配する
仏壇や位牌は、故人の魂が安らぐ場所、そしてご遺族が故人を偲ぶための大切な拠りどころです。故人の宗派や信仰する宗教に合わせたものを選びましょう。
位牌には、故人の俗名や亡くなった日付、戒名(仏門に入った証として与えられる名前)などを記します。
位牌は四十九日までに準備し、法要の際に僧侶に魂入れをしてもらいます。仏壇を新しく購入する場合は、故人の生前の希望や、ご自宅のスペースに合わせたサイズを選ぶことが重要です。準備が間に合わない場合は、一時的に仮の祭壇を設けることも可能です。
四十九日法要・納骨
四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる、仏教において重要とされる法要のひとつです。この日を境に故人の魂が来世へ旅立つとされているため、ご遺族や親族が集まり、冥福を祈ります。
法要を執りおこなう僧侶に連絡し、早めに日程を相談して依頼しましょう。会場は自宅やお寺、法要会館などが候補となります。日程と会場が決まったら、参列してほしい方に案内状を送るのが一般的です。
法要後には、参列者をもてなす会食場所を手配します。そして、感謝の気持ちを込めて、参列者に持ち帰ってもらうお礼の品である引き物の準備も忘れてはいけません。
四十九日法要の日に納骨もおこなう場合は、事前に墓石に故人の名前や戒名などを彫る文字彫りなども済ませておきましょう。
後回し厳禁!相続手続きの流れ
相続手続きは後回しにされがちですが、トラブルの原因となる可能性があるため放置は厳禁です。相続するか否かの判断や相続税申告には期限があるため、早めに着手しましょう。期限が迫って慌てないように、早めに専門家を頼ることも大切です。
1.遺言書の有無の確認
まず、故人が遺言書を残していないかの確認から始めましょう。遺言書は故人の意思が記された法的な書類です。遺言書がある場合、原則としてその内容にしたがって手続きを進めます。
遺言書は、自宅のほか、法務局や公証役場で保管されている可能性があります。自宅で遺言書が見つかった場合、改ざんや偽造を防ぐために、家庭裁判所での検認が必要です。もし遺言書を見つけたら、家庭裁判所や司法書士などの専門家に対応を確認しましょう。

2.相続人調査
戸籍謄本などを使って故人の出生から死亡までの全ての戸籍をさかのぼり、誰が法律上の相続人であるかを正確に把握します。配偶者や子が相続人となるケースが多いですが、子がいなければ父母や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
故人に離婚歴があったり養子縁組をしていたりすると、顔も知らない相続人の存在が判明する場合もあるため、戸籍の確認が重要です。調査を怠ると、あとから新たな相続人が見つかり、遺産分割協議をやり直すといったトラブルに発展するリスクがあります。
戸籍の見方がわからない場合や、戸籍を辿るのに行き詰ってしまった場合は、市区町村の戸籍担当課や行政書士などの専門家に相談しましょう。
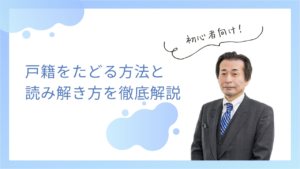
3.相続財産調査
相続人を確定したら、次は故人の財産を全て洗い出す作業です。故人の財産には、預貯金、不動産、株式、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。プラスとマイナスの財産を全て把握し、財産目録を作成しましょう。
特にマイナスの財産の有無や金額は、相続の方法を決定する際の重要な判断基準となります。事業の借入金や連帯保証債務、消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの未払い金など、徹底的な調査が求められます。信用情報機関に照会するのも有効です。

4.相続の方法を決定
相続の方法は、プラスもマイナスも全ての財産を無制限に相続する「単純承認」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」、全ての財産を相続しない「相続放棄」の3つがあります。財産調査の結果を受けて方針を決めましょう。
相続放棄と限定承認は、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。適切な選択ができるかどうかは、財産調査にいかに早く着手できるかにかかっています。
相続放棄は相続人ひとりひとりがおこなえる一方、限定承認は相続人全員でおこなう必要があります。家庭裁判所に申立てたあとも、官報公告や債務弁済手続きなどが煩雑なため、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
5.遺産分割協議
遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をおこないます。この話し合いでは、誰がどの財産を相続するか、相続人全員の合意が必要です。
話し合いがまとまったら、後々のトラブルを避けるために、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。不動産や預貯金の名義変更手続きの際に必要な重要な書類です。署名捺印する際は、内容をよく確認してからおこないましょう。
6.名義変更手続き
遺産分割協議書を作成したら、いよいよ故人名義の財産を相続人の名義に変更する手続きをおこないます。
不動産の場合は、法務局で所有権移転登記をおこないます。預貯金の場合は、金融機関の窓口で名義変更や払い戻しの手続きをします。自動車の場合は、陸運局で名義変更手続きが必要です。
登記は司法書士に、その他の名義変更手続きは行政書士に依頼して代行してもらうことも可能です。手続きが多岐にわたり負担に感じる場合は、専門家に相談するとよいでしょう。
7.相続税の申告と納税
相続した財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納税が必要となります。申告期限は、故人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の計算は非常に複雑で専門的な知識が必要なため、税理士への相談を検討しましょう。相続税は現金で一括納付が原則です。相続財産に不動産や株式などが多く現金が少ない場合は、納税資金の確保も課題となります。

専門家に相談して円滑に手続きを進めよう
相続手続きは専門知識が必要な場面が多いうえに、相続人同士の連絡や書類の取得など短期間でやることが多く、自力で対応するのは困難な場合も多いものです。
しかし、放置すると、相続放棄のタイミングを逃して借金を背負ったり、相続税申告を怠って税務署から指摘を受けたりするリスクがあります。
登記は司法書士、相続税は税理士に相談しましょう。相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きは、行政書士が対応可能です。困ったら専門家を上手に活用するのが円滑な手続きの鍵です。

まとめ
葬儀後には、悲しむ間もなく多くのやるべきことがあります。本記事を参考に、やることを一覧にしてひとつずつ着実におこないましょう。
特に、相続手続きは自分で進めるのが難しい場合も多く放置してしまいがちですが、最悪の場合は自身の財産や生活が脅かされるリスクがあります。ひとりで進めるのが難しいと感じたら、迷わずに専門家を頼りましょう。まずは無料相談で話を聞いてみるのもひとつの方法です。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続に関する相談を受け付けています。何から始めていいかわからない方、どこに相談すればよいかわからない方もお気軽にお問い合わせください。









