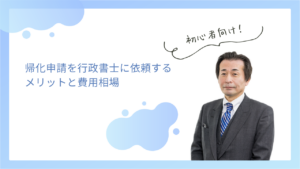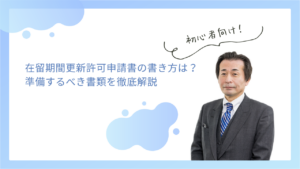【2025年10月16日施行】経営管理ビザの改正内容は?行政書士が徹底解説

令和7年10月16日より、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に厳格化されることが決定しました。
今回の改正は、新規申請者だけでなく、すでにビザを持って日本で事業を行っている方の更新や、将来の永住申請にも深刻な影響を与えます。
本記事では、行政書士佐藤秀樹事務所が、今回の改正で何が変わり、誰が影響を受けるのか、そしてあなたが「今すぐやるべき対策」は何かを、ポイントを絞って徹底的に解説します。
【重要】経営管理ビザが大幅に厳格化されました
令和7年10月10日に公表(同月16日更新)され、令和7年10月16日から施行される改正により、この「経営・管理」ビザの許可基準が大幅に厳格化されることが決定しました 。
これは単なる微調整ではなく、従来の「資本金500万円」といった基準が根底から見直され 、事業の「本気度」と「継続性」が厳しく問われる、まさに抜本的な改正です。
参照:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)
何が変わる?5つの重大な変更点
これまで「資本金500万円」がスタンダードだった経営・管理ビザですが、今回の改正で基準が根本から見直されます 。いったい何が、どのように変わるのでしょうか。
特に影響の大きい「5つの重大な変更点」を、現行制度と比較しながら解説します。
1. 資本金の金額が500万円から3,000万円へ引き上げ
事業の規模に関する要件が大幅に引き上げられ、3,000万円以上の資本金等が必要になります。
| 法人の場合 | 株式会社の払込済資本の額(資本金の額)や、合同会社等の出資の総額をさします。 |
| 個人の場合 | 事業所の確保、雇用する職員の給与(1年分)、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額をさします。 |
従来の500万円から6倍もの増額となり、新規参入のハードルが劇的に上がりました。単にお金を用意するだけでなく、その「出所」や「形成過程」の立証も、これまで以上に厳しく審査されることが予想されます。
2. 常勤職員1名以上の雇用が必須に
これまでは必須要件ではありませんでしたが(資本金の代替要件としては存在)、改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
この改正で最も注意すべきは、この「常勤職員」の対象者です。対象は、日本人、特別永住者、及び「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった法別表第二の在留資格を持つ者に限られます。
つまり、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで外国人を雇用しても、この要件は満たせないことになります。日本国内での安定した雇用を生み出すことが、経営者に明確に求められる形となりました。
3. 経営者の経歴として「3年以上の経営経験」または「修士以上の学位」が求められるように
いままでは必須要件ではありませんでしたが、改正後は経営者本人の適格性が厳しく問われます。以下のいずれかを満たす必要があります。
- 事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること
- 経営管理又は申請に係る事業分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること
1つ目の要件については、「特定活動」に基づく起業準備活動の期間も含むことができます。2つ目の要件では、外国で授与されたこれに相当する学位も含まれます。
「経営経験」をどう客観的に証明するか、ご自身の学位が「関連分野」と認められるかなど、専門的な知識に基づいた立証準備が不可欠です。
4. 申請者または常勤職員に「N2相当」の日本語能力を要求
新たに日本語能力に関する要件が加わりました。申請者(経営者)又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」B2相当以上)を有することが必要になります。
具体的には、以下のいずれかに該当することが求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けていること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得していること
- 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
- その他、日本での20年以上の在留、日本の義務教育・高校卒業など
経営者ご本人にN2相当の能力がなくても、雇用する常勤職員が要件を満たせばクリア可能です。
なお、この日本語能力要件で対象となる「常勤職員」には、上記2の雇用義務とは異なり、法別表第一の在留資格(「技・人・国」など)をもって在留する外国人も含まれます。制度が非常に複雑なため、注意が必要です。
5. 事業計画書は中小企業診断士など専門家の確認が義務化
在留資格決定時(主に新規申請時)に提出する事業計画書について、その計画に「具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであること」を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます。
この「専門家」とは、施行日時点では以下の資格者を指します。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
単に計画書を作るだけでなく、これらの専門家(士業)と連携し、入管を納得させられる「実現可能性」の高い事業計画を策定する必要があります。当事務所のような在留資格専門家と、これらの士業との連携が、今後のビザ取得の鍵を握ります。
【パターン別】今すぐ確認すべきこと
今回の重大な改正は、あなたの現在の状況によって「今すぐやるべきこと」が大きく異なります。
ご自身がどのパターンに当てはまるか、ここで直ちに確認してください。
【パターン1】これから「経営・管理」ビザを申請する方(新規申請)
令和7年10月16日以降に、新規で在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)や在留資格変更許可申請(国内で他ビザから切り替える場合)を行う方は、即座に改正後の新しい許可基準が適用されます。
したがって、申請準備の段階で、以下のすべてをクリアしている必要があります。
| 資本金 | 3,000万円以上 |
| 雇用要件 | 1人以上の常勤職員(日本人、永住者等) |
| 経歴 | 3年以上の経営・管理経験、または修士相当以上の学位 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員がN2相当以上の能力 |
| 事業計画 | 税理士などの専門家が確認した事業計画書 |
従来の「資本金500万円で会社設立」という方法は通用せず、事業計画の策定から資金調達、人材確保まで、以前とは比較にならない高度な準備が求められます。
【パターン2】既に「経営・管理」ビザで在留中の方(更新申請)
すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方(「高度専門職1号ハ」を含む)は、3年間の経過措置(猶予期間)が設けられています。
施行日から3年以内(令和10年10月16日まで)の更新申請
この期間中に行う更新申請については、新しい基準に適合していない場合でも、直ちに不許可になるわけではありません。現在の経営状況や、「改正後の許可基準に適合する見込み」などを踏まえて、総合的に許否判断がなされます。
なお、審査の過程で、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
3年経過後(令和10年10月16日以降)の更新申請
猶予期間が終了した後の更新申請では、原則として改正後の新しい許可基準(資本金3,000万円、雇用義務など)に適合する必要があります。
「まだ3年ある」と考えるのは非常に危険です。3年後に「常勤職員を雇用できていない」「事業規模が基準に満たない」という事態になれば、在留資格を失うリスクに直結します。今すぐに3年後の更新を見据えた事業計画の見直しと実行に着手すべきです。
【パターン3】「経営・管理」ビザから永住許可を申請する方
「経営・管理」ビザをお持ちで、将来の「永住」を考えている方には、最も厳しい内容となります。
施行日(令和7年10月16日)以降、改正後の新しい許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」ビザ(及び関連する高度専門職ビザ)からの永住許可は認められません。
永住許可申請には、更新申請のような3年間の猶予措置(経過措置)はありません。永住を目指す経営者の方は、施行日以降、資本金3,000万円(またはそれに準ずる事業規模)、常勤職員の雇用といった新基準を速やかにクリアすることが必須条件となります。
各改正点の詳細と「つまずきやすい」ポイント
今回の改正内容は、ただ読むだけでは見落としてしまう「落とし穴」が数多く隠されています。
在留資格の専門家として、特に注意すべき「つまずきやすいポイント」を詳細に解説します。
資本金の引き上げについて
改正後は、3,000万円以上の資本金等が必要になります。法人の場合は「払込済資本の額」、個人事業主の場合は「事業を営むために投下されている総額」(事業所経費、職員給与1年分、設備投資など)を指します。
従来の500万円でも、その資金を「どうやって形成したか」は厳しく審査されていました。これが3,000万円になることで、審査の厳格さは格段に上がると予想されます。単に通帳に3,000万円があるだけでは不十分です。
見せ金(一時的な借り入れ)は絶対にせず、融資や自己資金、出資など、その資金形成の合理的なプロセスを、客観的な資料ですべて立証する必要があります。
雇用義務の定義について
改正後、1人以上の「常勤職員」を雇用することが義務付けられます。
「常勤職員」になれる人、なれない人、これが最大の落とし穴です。この雇用義務でいう「常勤職員」の対象は、以下の者に限られます。
- 日本人
- 特別永住者
- 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人
つまり、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(法別表第一の在留資格)で働く外国人を雇用しても、この要件は満たせません。日本国内の雇用(日本人や永住者等)を生み出すことが、経営者に明確に求められる形となりました。
経営者の経歴について
申請者(経営者)本人に、一定の適格性が求められるようになりました。
「3年間、経営者だった」と口で言うのは簡単ですが、入管は客観的な証拠資料を求めます。例えば、海外の会社での経験を証明する場合、役員として登記されていた登記簿謄本や、具体的な職務内容が明記された在職証明書、組織図などが必要になります。これらの準備は非常に煩雑です。
「経営・管理経験」の客観的な立証ができるよう、準備を進めておきましょう。
日本語能力の要件について
申請者(経営者)または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR B2相当)を有することが必要です。
要件を満たす「職員」の範囲が非常に複雑です。申請者本人がN2を持っていなくても、常勤職員が持っていれば良いのですが、この日本語能力要件に限っては、その「常勤職員」の対象に「技術・人文知識・国際業務」など(法別表第一)の外国人社員も含まれます。
これを整理すると、「雇用義務」の1名は日本人・永住者等でなければなりませんが、「日本語能力」を満たすためのスタッフはN2持ちの外国人社員でも良い、ということです。ここは複雑な話になってしまうので、気になる場合は在留を得意とする専門家(行政書士など)に聞いてみましょう。
事業計画書について
新規申請時などに提出する事業計画書について、その「具体性、合理性、実現可能性」を担保するため、経営の専門家による確認が義務付けられます。
ここでつまずきやすいのは、「行政書士と他士業との役割分担」です。入管当局は「弁護士及び行政書士以外の方が、報酬を得て申請書等の書類作成を業として行うことは、行政書士法違反のおそれがある」と明記しています。 つまり、ビザ申請書類の作成・提出代行は行政書士の独占業務です。
今後の申請では、「ビザ申請のプロ=行政書士」と「経営計画のプロ=税理士等」のスムーズな連携が、許可取得に欠かせなくなりました。当事務所では、これらの専門家と緊密に連携し、入管法と経営合理性の両方を満たした、許可率の高い申請をサポートします。
まとめ
今回の「経営・管理」ビザの大幅な改正は、単なるハードルの引き上げではありません。
これは、日本で「本気で事業を成長させ、安定した雇用を生み出し、公租公課(税金や社会保険料)を適切に納める意思のある経営者」を明確に選別するという、出入国在留管理庁の強いメッセージです。
特に、「常勤職員」の定義や、事業計画書における専門家の確認など、制度は非常に複雑化しています。さらに、永住許可を申請する場合は、この新しい基準を施行日以降すぐに満たしていなければなりません。
「自分の場合はどうなる?」「3年後に向けて何を準備すれば?」など少しでも不安を感じたら、その判断があなたの将来の在留資格を左右します。手遅れになる前に、在留資格のプロフェッショナルである行政書士佐藤秀樹事務所にご相談ください。