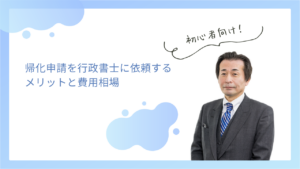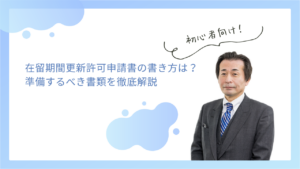在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件とリスク回避策

外国人が日本で専門性の高い仕事をするためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要です。
「海外の優秀な人材を雇用したいが、手続きが複雑で不安」「日本の大学を卒業後に日本で働きたいが、在留資格の変更要件がわからない」—–このようなお悩みをお持ちの企業や外国人の方も多いでしょう。
本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基礎知識から、申請者と企業が満たすべき要件、リスク回避策まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。
企業は優秀な人材確保のために、外国人の方は日本でのキャリア形成のために、複雑な申請要件を正しく理解しましょう。
※外国人が日本で専門性の高い仕事をするための在留資格は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)および関連する省令で定められています。
「技術・人文知識・国際業務」の基礎知識
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて以下のような専門性の高い業務に従事するためのビザです。略して「技人国(ぎじんこく)ビザ」とも呼ばれます。
| 分野 | おこなう業務 | 具体例 |
| 技術 | 理学、工学その他の自然科学の分野に関する専門知識・技術を要する業務 | システムエンジニア(SE)、プログラマー、機械設計、建築設計、品質管理、研究開発、各種エンジニアなど |
| 人文知識 | 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に関する専門知識を要する業務 | 企業の企画、広報、経理、マーケティング、営業、弁護士補助業務、コンサルタントなど |
| 国際業務 | 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務 | 通訳、翻訳、語学教師、デザイナー、海外取引業務、広報、ファッション・インテリアなどの商品開発など |
技人国ビザは、ITエンジニア、研究者、コンサルタント、通訳、デザイナーなどの幅広い職種が対象で、外国人材受け入れの中心的役割を担っています。
広報や海外営業など、両分野の知識が関わる業務は、その専門性の割合により「人文知識」または「国際業務」に該当します。
技術分野(ITエンジニア・研究職など)
技術分野は、情報処理技術、機械工学、電子工学、建築学、化学などの専門知識や技術を応用する職種が該当します。代表的な職種は、ITエンジニア、製品開発エンジニア、研究者、建築設計士などです。
技術分野で在留資格を取得するには、原則として、日本の大学などで自然科学系の科目を専攻し卒業していること、または10年以上の実務経験が必要です。業務内容と専門性が関連していること問われます。
人文知識分野(経理・営業・マーケティング職など)
人文知識分野は、法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を必要とする業務を指します。具体的には、企業の経営管理、経理、財務、人事、営業、マーケティング、企画、広報などです。専門知識やスキルを活かして企業活動を担うことが期待されます。
人文知識分野の場合も、原則として日本の大学などで人文科学系の科目を専攻し卒業していること、または10年以上の実務経験が求められます。業務の内容が単なるルーティンワークではなく、専門的な知識やスキルを要するかどうかがポイントです。
国際業務分野(通訳・デザイナー・語学講師など)
国際業務分野は、技術分野・人文知識分野とは異なり、外国語能力や外国での経験を活かす仕事が中心です。具体的には、通訳・翻訳、語学の指導、海外取引業務、デザイナーなど、外国の文化や感性を必要とする業務が該当します。
国際業務分野の許可要件は、原則として「従事しようとする業務について3年以上の実務経験」を積んでいることですが、大学卒業者には例外があります。
従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
したがって、例えばデザイナーや海外取引業務(翻訳・通訳を除く)などの職種では、この3年間の実務経験を証明する書類の準備が非常に重要になります。
高度専門職・特定活動へのステップアップ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本でのキャリアを積むことで、上位の在留資格である「高度専門職」や、特定の条件下で認められる「特定活動」にステップアップできます。
「高度専門職」は、学歴・職歴・年収などの要素をポイント化して70点以上に達することで、在留期間の優遇や永住許可の要件緩和などの優遇措置を受けられる在留資格です。
一方、「特定活動」は、ワーキング・ホリデーやインターンシップ、起業準備など、個別の活動内容に応じて法務大臣が指定する活動を行うための在留資格です。
特に、日本の大学を卒業した留学生が就職活動を目的とした在留期間延長のために利用できる「特定活動」や、特定の業種で就職できる「特定活動46号(本邦大学卒業者)」など、技人国ビザの要件を補完・緩和する制度として機能する場合もあります。
日本での長期的なキャリア形成を望む場合、将来的には技人国ビザからのステップアップも検討するとよいでしょう。
申請者個人の許可要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、職務内容が専門的であることに加え、申請者個人に専門業務を遂行するための能力が求められます。申請者の能力は、主に学歴や実務経験によって証明します。出入国在留管理庁の審査で疑義が生じないよう、証明書類などを準備しておきましょう。
大卒・専門学校卒
日本の大学または外国の大学を卒業していることが一般的かつ強力な学歴要件です。専攻した科目と従事する業務内容との間に関連性があることが求められます。
たとえば、経済学部出身者が経理や営業の仕事に就く場合は関連性が認められやすいでしょう。一方、文学部出身者がITエンジニアの仕事に就く場合は、専攻内容だけでは関連性を証明することが難しくなります。
専攻と業務内容の関連性がない場合は絶対にビザ取得が認められないかというと、そうではありません。大学で履修した関連科目の詳細や、入社後の研修計画などにより、補完的に能力を証明することも可能な場合があります。
また、日本の専修学校の専門課程を修了した場合も在留資格の申請資格があります。専門士の場合、専門学校で学んだことが業務にどのように活かされるのかを具体的に説明する必要があります。
また、専修学校は、法務大臣が告示をもって定める要件に適合しているもの(原則として修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上)であることが必要です。専門学校での専門知識が、入社後の職務にどのように活かされるのかを具体的に説明することが不可欠です。
実務経験者の特例
原則として10年以上の実務経験がある場合、大学や専門学校を卒業していない場合でも能力の証明が可能です。国際業務分野(通訳・翻訳、デザイナーなど)に限り、3年以上の実務経験で要件を満たします。
単にその期間働いていたという事実はもちろんのこと、専門知識やスキルを習得・向上させてきたことを具体的に証明する必要があります。以前の勤務先の在職証明書だけでなく、職務内容の詳細、成果物などをまとめておくとよいでしょう。ポートフォリオがあると専門性を示しやすくなります。
大学院卒の優遇措置と注意点
日本または外国の大学院を修了している場合は、高度な専門知識を有することの証明となり、高度専門職のポイント計算を行う際にも有利です。
ただし、専門的な知識をほとんど必要としない業務に従事する場合は不許可となる可能性があります。高度な学歴に見合った、専門性が求められる業務に従事することが大前提です。
外国人留学生が在学中にすべきこと
外国人留学生が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へスムーズに切り替えるためには、在学中からの準備が大切です。卒業後に従事しようとする職務内容に直結する専門知識を深く習得しましょう。研究成果を示す卒業論文などは重要な資料となります。
留学中に資格外活動許可を得てアルバイトをする場合、将来の職務に関連する分野での経験を積むことで審査の際に有利に働く可能性があります。内定を得た後は、企業と連携して職務内容説明書を準備しましょう。
不許可事例とリスク回避策
在留資格の申請は、法律に基づき厳格な審査がおこなわれます。不許可となると、就労の予定が遅れるばかりか、最悪の場合、日本での就労自体が不可能になるリスクがあります。不許可事例から学び、事前に適切な対策を講じましょう。
【事例1】専攻と職務内容が合わないと判断されたケース
日本の大学で日本文学を専攻した外国人留学生が、日本国内のIT企業からシステムエンジニアとして内定を得て、在留資格の変更申請をおこなったところ、不許可となりました。専攻とシステムエンジニアの業務内容との間に専門的な関連性がないと判断されたためです。
内定企業が提出した職務内容説明書には、ITの専門知識が必要な業務が記載されていました。一方、申請者からはITに関する専門科目の履修履歴や、職業訓練、実務経験を裏付ける十分な証拠が提出されていませんでした。
専攻と業務内容の関連性が薄いと判断されそうな場合は、職業訓練や企業研修の履修や、インターンシップなどの実務経験の証明が追加で求められます。また、企業側と連携し、業務内容の中で専攻分野の知識が活かされる側面がある場合は重点的に説明することも有効です。
【事例2】実務経験の証明が不十分で不許可になったケース
海外で営業職として10年間の勤務経験をもつ外国人が、日本国内の企業から営業職で内定を得て在留資格申請をおこなったところ、実務経験の証明が不十分として不許可となりました。不許可理由は、過去に経験した具体的な職務内容や、職務遂行に必要な知識・スキルが明確に示されていなかったためです。
単に営業職で働いていたという事実だけでは、人文知識分野の専門的知識を要する10年間の実務経験とは認められません。実務経験を証明する際は、どのような専門的な知識(財務分析、国際契約に関する知識など)を要する業務に携わったか具体的に提示しましょう。
たとえば、詳細な職務経歴書や、組織図、関わったプロジェクトの概要などを用意します。また、過去の勤務先の上司など、業務内容を具体的に知る第三者からの補足説明書を提出してもらうことも有効です。
【事例3】過去の在留状況に問題があったケース
過去に留学生として日本に在留していた際、在留期間を超過して日本に滞在していた(オーバーステイ)経歴がある外国人が、一度母国に帰国し、あらためて在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請したところ、不許可となりました。不許可理由は、入管法上の「上陸拒否事由」に該当する過去の不法残留(オーバーステイ)の事実が判明したためです。
在留資格の審査では、申請者個人の素行も重要な審査対象です。過去に日本の法令に違反した履歴がある場合、在留資格の取得や更新に重大な悪影響を及ぼします。万が一、過去に法令違反がある場合は、正直に申請し、反省と再発防止の陳述書を提出する必要があります。
法令違反の重大性にもよりますが、違反行為から現在までの期間が長ければ長いほど、再犯のリスクが低いとみなされる傾向があります。過去の在留状況に問題がある場合は、個人で対応するのは困難なため、行政書士などの専門家への相談をおすすめします。
企業側の許可要件とリスク管理
申請者である外国人本人だけでなく、雇用主となる日本企業側が満たすべき要件も多岐にわたります。スムーズに優秀な人材を採用するためには、企業側が適切なリスク管理をおこない、法務を遵守することが大切です。ここでは、企業側の許可要件について解説します。
事業の安定性・継続性はあるか
企業が外国人社員を雇用し、長期的に専門業務に従事させるために、企業自体の事業の安定性と継続性が求められます。評価される要素と判断基準の例は以下のとおりです。
| 評価要素 | 具体的な判断基準(例) | 必要な書類(例) |
| 財務状況 | 直近の経営状況(売上高、利益など)、債務超過ではないか、適切な納税を行っているか | 損益計算書、貸借対照表(直近年度の決算報告書)、法人事業税及び法人住民税の納付済証 |
| 事業規模 | 従業員数、資本金など。設立直後の企業は事業計画の妥当性が問われる | 会社案内、商業登記簿謄本、事業計画書(設立から間もない場合) |
| 事業実績 | 過去の実績と将来の見込み。新規事業の場合は、具体的な事業計画と収支見込みが求められる | 会社案内、主要な取引先との契約書など |
設立間もない企業や、赤字が続いている企業は、事業計画の具体性や、外国人社員の採用が企業の成長にどのように貢献するのかを、より詳細かつ論理的に説明する必要があります。
報酬の適正性はあるか
外国人社員に支払われる報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。外国人を不当に低い賃金で雇用することを防ぐためです。
具体的には、社内の同等の職種・経験年数の日本人社員と比べて不当に低い金額ではないこと、地域や職種の一般的な報酬水準を下回らないことが重要です。
判断基準となる報酬の金額には、通勤手当や扶養手当などの実費弁償的な手当は含まれません。基本給、役職手当、専門職手当など、純粋に専門業務をおこなう対価として支払われる部分のみが対象となる点に注意しましょう。雇用契約書や賃金台帳を提出し、報酬の適正性を客観的に証明する必要があります。
専門的な業務量と契約上の注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るためには、外国人社員が従事する業務の専門的な内容であることと、その業務が安定的に継続しておこなわれるだけの十分な業務量があることが必要です。業務全体に占める専門的な業務の割合としては、おおむね50%以上が目安です。
たとえば、システム開発を専門とする人材であるにもかかわらず、業務の大部分は単純な事務作業や清掃などの雑務である場合は不許可となります。雇用契約書には、従事させる具体的な業務内容を記載し、技術・人文知識・国際業務のいずれかの分野に該当する専門業務であることがわかるようにしましょう。
採用後の配置転換や昇進によって専門的な業務から外れる可能性がある場合は、その都度、在留資格の変更や再申請が必要になるリスクも理解しておく必要があります。
入管への届出義務
外国人社員を雇用する企業には、入管法に基づき、外国人社員の在留資格に関連する重要な変更があった場合に、出入国在留管理庁へ届け出を行う義務があります。また、外国人社員本人も届出義務を負います。
主な届出事項は以下のとおりです。
| 届出事項 | 届出義務者 | 届出期限 | 罰則(義務違反の場合) |
| 受入れ(雇用)開始 | 企業(所属機関) | 雇用開始から14日以内 | ※1 |
| 契約終了(離職・解雇) | 企業(所属機関) | 契約終了から14日以内 | ※1 |
| 在留資格の変更等 | 外国人社員本人 | 変更から14日以内 | 20万円以下の罰金 |
| 住居地の変更 | 外国人社員本人 | 変更から14日以内 | 20万円以下の罰金 |
※1 企業側の罰則について 入管法上の直接的な罰則規定はありませんが、届出を怠ると「法令遵守の状況が悪い」とみなされ、次回の外国人雇用やビザ更新審査で不利になる可能性があります。(なお、ハローワークへの届出を怠った場合は、雇用対策法に基づき30万円以下の罰金となる可能性があります)
一方、外国人本人には以下の罰則が明確に定められています。
【入管法第71条】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
外国人を採用する場合は、事前に社会保険労務士や行政書士に相談すると安心です。
企業側の不許可リスクと対応策
企業側の要因で在留資格が不許可となる場合もあります。確実に在留資格を得られるよう、失敗事例からリスクと対策を学びましょう。
【事例1】企業の経営状況が不安定と判断されたケース
設立から3年未満のIT企業が外国人エンジニアを採用しようと在留資格申請をしたが、直近の決算が2期連続の赤字で、資本金も減少傾向にあったため不許可となりました。企業側に外国人社員を雇用するだけの体力と、業務を継続的に提供できる基盤がないと判断されたためです。
赤字が続いている場合、外国人社員への安定的な報酬支払いや事業継続性を不安視されるリスクがあります。赤字の原因を分析し、今後どのように事業を黒字化していくかを記載した事業改善計画書を示す方法もあります。金融機関からの融資証明や増資の証明など、事業継続のための資金調達ができていることを示す資料の提出も有効です。
また、採用する外国人社員の専門知識や技術が企業の成長に不可欠であることを説明し、採用の緊急性と必要性を訴えましょう。
【事例2】外国人社員への報酬が不適正と判断されたケース
外国人社員に対し、同じような職務に従事する日本人社員よりも基本給が低い雇用契約を結び、在留資格を申請した結果、不許可となりました。日本人と同等額以上という報酬要件を満たしていないことが明確な不許可理由です。
企業がコスト削減を目的に外国人を不当に安価に雇用することがあってはなりません。外国人社員の基本給が日本人社員と同等額以上となるように雇用契約書をただちに見直しましょう。
そのうえで、比較対象となる日本人社員の職務内容、経験年数、役職などを明確にし、その賃金水準と外国人社員の報酬が同等であることを説明します。報酬の内訳も明らかにし、専門業務の対価としての基本給や専門職手当が適正であることを示しましょう。
【事例3】過去に労働基準法や入管法違反があったケース
過去に長時間労働に関する労働基準監督署からの是正勧告を受けていた企業が、新たな外国人採用の申請を行ったところ、審査が長期化し、最終的に不許可となりました。
企業のコンプライアンス体制は、在留資格審査において極めて重要です。過去に労働関係法令や入管法(不法就労の助長など)の違反があった場合、外国人社員を適正に雇用・管理できる体制がないと判断され、不許可のリスクが大幅に高まります。
万が一、過去に法令違反の履歴がある場合、具体的な再発防止策を策定し実行していることを示す詳細な改善報告書を提出します。弁護士や社会保険労務士などの専門家からの意見書を添付し、企業が真摯に改善に取り組んでいることを客観的に証明することも有効です。
法令違反の重大性によっては、一定期間は外国人採用を控えるなど、リスクを回避するための戦略的な判断も必要です。
失敗しない!新規・変更・更新の手続き方法
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請は、新規採用、留学生からの変更、継続就労のための更新と、フェーズによって手続きが異なります。いずれの場合も、法律で定められた要件を正確に理解し、適切な準備をおこなうことが大切です。それぞれの場合の手続き方法について見ていきましょう。
新規採用時の手続き
海外在住の外国人を新たに採用する場合や、すでに別の在留資格(例:短期滞在)で日本にいる外国人を採用する場合の手続きです。
まず、企業側が地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」をおこないます。この証明書は、外国人が日本でおこなう活動が入国の条件に適合していることを証明するものです。
認定証明書が交付されたら母国にいる外国人本人に送付し、本人が現地の日本大使館・総領事館でビザ(査証)の申請をおこないます。ビザが発給された後、外国人は日本に入国し、空港などで在留カードが交付され、就労が可能になります。手続きかかる時間は一般的に2〜3ヶ月程度です。
留学生からの切り替え
日本の大学や専門学校を卒業する外国人留学生を採用する場合、「在留資格変更許可申請」が必要です。卒業見込みの時期に合わせて、卒業前から申請の準備を開始します。
審査の重要なポイントは、卒業した学校での専攻科目と、内定先の企業で従事する業務内容との間に専門的な関連性があるかどうかです。専門学校卒業(専門士)の場合は、学校の課程が法務大臣告示の基準を満たしていることも要件です。
申請をおこなうのは留学生本人ですが、内定企業が提出する雇用契約書、職務内容説明書などの書類が審査の鍵を握ります。企業と申請者が密に連携をとり、準備を進めましょう。
更新許可申請
すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が、現在の企業での就労を継続するために行う手続きです。在留期限の3ヶ月前から申請が可能です。
審査のポイントは、過去の在留期間において、許可された専門業務を適正におこなっていたか、雇用する企業の経営状況が悪化していないか、外国人本人と企業側が法令を遵守していたかの3点です。
転職していない場合でも、企業の名称や所在地、代表者などに変更があった場合は、入管への届出が適正に行われているかを確認し、更新申請に臨みましょう。
もし不許可通知を受けたら
万が一、不許可通知を受け取った場合、数日以内に出入国在留管理庁へ出向いて不許可理由を聞きましょう。行政書士などの専門家に同行してもらうことも可能です。
不許可理由が書類の不備や説明不足など比較的容易に解消できる事項の場合は、不備を解消したうえですぐに再申請ができます。
再申請でも許可の見込みがない場合、不許可事由に納得いかなければ、行政不服審査法に基づく審査請求や、裁判所への行政訴訟を提起することも可能です。ただし、法的手段は専門的な知識が必要なうえ、時間も労力もかかります。弁護士に相談のうえ、慎重に判断しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」取得後のキャリアデザイン
在留資格を取得したあとも、転職、家族の呼び寄せ、将来的な永住権の取得など、日本に在留する期間のライフイベントは在留資格と密接な関わりがあります。活動内容に変更が生じる際には、必ず入管法に基づく手続きが必要です。制度をしっかり把握し、日本での安定したキャリアと生活を守りましょう。
転職時の在留資格の見られ方
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人が転職する場合、外国人本人・転職元企業・転職先企業のそれぞれに届出義務が発生します。
- 転職元の企業: その外国人が離職(契約終了)した日から14日以内に、「中長期在留者の受入れに関する届出」をおこなう義務があります。
- 外国人本人: 新しい会社での活動を開始した日から14日以内に、「所属(契約)機関に関する届出」をおこなう義務があります。
- 転職先の企業: その外国人の受入れ(雇用)を開始した日から14日以内に、「中長期在留者の受入れに関する届出」をおこなう義務があります。
また、「就労資格証明書交付申請」により、転職後の業務内容が現在の在留資格の活動範囲内であることを証明してもらうことが可能です。必須ではありませんが、次回の在留期間更新申請の際に審査がスムーズに進む可能性が高まります。
転職後の在留期間更新申請では、前職から転職した理由や、転職後の業務内容の専門性、転職先の企業の安定性などが新規申請時と同様に厳しく審査されます。
特に、許可取得から1年未満での短期間での転職を繰り返している場合や、転職によって業務の専門性が低下していると判断された場合は、更新が不許可になるリスクがあるため注意が必要です。
副業・兼業を行う際の原則と届出義務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、原則として許可された活動(本業)をおこなうことを前提としています。許可された範囲内であれば副業・兼業は可能ですが、専門的な知識やスキルを活かす活動であることが前提です。
たとえば、本業がITエンジニアの方が別の企業でITコンサルティングの業務をおこなうなど、副業・兼業の活動が本業と同じ在留資格の活動内容と同一である場合、原則として「資格外活動許可」は不要です。
ただし、少しでも業務内容が異なる場合は資格外活動許可が必要となるリスクがあるため、事前に専門家に相談することを推奨します。
副業をする場合も、あくまでも本業が主たる活動であることを念頭に置きましょう。
家族滞在ビザについて
外国人社員が家族を日本に呼び寄せるために「家族滞在」の在留資格を申請することができます。対象者は配偶者(夫または妻)と子供(子)に限られ、兄弟姉妹や両親は対象外です。
申請者である外国人本人が、家族を日本で扶養できるだけの十分な収入と経済力があることが必須要件です。また、本国で発行された婚姻証明書や出生証明書など、関係性の公的な証明が求められます。
家族滞在の在留資格をもつ家族は、原則として就労活動はできませんが、資格外活動許可を得た場合は、週28時間以内という時間制限のもとで就労が可能です。
永住権へのステップアップ
永住権は、在留期間や活動内容の制限がない在留資格です。
主な要件は、以下のとおりです。
- 日本に引き続き10年以上在留していること
- 5年以上、就労資格または居住資格をもって在留していること
- 犯罪歴がなく日本の法令を遵守していること
- 安定した職業と家族を養える十分な収入があること
- 納税義務などを履行していること
「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」の在留資格へ切り替えた場合、永住権の申請に必要な在留期間の要件が1年または3年に短縮されます。永住権へのステップとしてまずは「高度専門職」への切り替えを検討する方も多いです。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な業務に従事する外国人のための在留資格です。外国人本人だけでなく、雇用する企業側にも要件があり、特に、専門分野と業務内容の関連性を明確に示すことが重要なポイントとなります。
申請に向けて双方が密に連携し、計画的に準備を進めましょう。申請要件を満たすか不安な場合は、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、在留資格申請についてのご相談を受け付けています。申請書類の確認や申請の代行など、外国人を雇用したい企業の方をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。