疎遠な親が亡くなっても連絡は来ない?知らないうちに相続が進むリスクと対処法

親と長期間音信不通であった場合、親が亡くなったことを知ることなく時が過ぎることも少なくありません。しかし、その間に相続手続きが進行している場合、あとから不利益を被るリスクがあることをご存じでしょうか?
親が亡くなったことを知らずにいることで、相続放棄の期限を過ぎてしまう、相続税の申告を逃してしまう、さらには遺産分割が進んでしまうといった問題が発生することもあります。本記事では、親の死を知らなかった場合に直面するリスクや、その対処法について詳しく解説します。
親と音信不通でも死亡時に連絡は来るの?

親と長期間にわたって連絡を取っていない方も珍しくありません。音信不通の親が亡くなった場合、必ずしも連絡が来るとは限りません。ただし、あなたの連絡先が判明すれば、警察や市区町村、親族から連絡が来るケースもあります。
自動的に連絡されるシステムは基本的にない
親と音信不通の状態が続いている場合、親が亡くなった際に自動的に死亡の連絡が届くシステムは基本的に存在しません。死亡届が提出されても、法的に相続人に連絡が来ることはなく、相続手続きに関する通知は届かないことがほとんどです。そのため、親の死を知らずに時が過ぎる可能性もあります。
連絡が来る可能性があるケース
親が亡くなった経緯や相続手続きの状況によっては、親と疎遠にしていても亡くなった旨の連絡が来る可能性があります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
警察から連絡が来るケース:事件性がある場合や身元確認

親が自宅などで孤独死した場合や、事件や事故に巻き込まれて亡くなった場合、警察が関与します。特に、独り暮らしの高齢者が自宅で亡くなっていたケースなどでは、事件性がないかの確認や身元確認が必要になる場合があります。警察の調査によって連絡先が判明すれば、疎遠にしていても連絡が来る可能性はあります。
市区町村役所から連絡が来るケース:孤独死や引き取り手がない場合

孤独死の場合など、亡くなった方の親族と連絡がとれない場合は、警察から市区町村に連絡が行きます。亡くなった方の身元が判明している場合は、市区町村役所から親族に遺体の引き取りを求める連絡が来る場合があります。親族が遺体の引き取りを拒否した場合、市区町村が火葬し、遺骨を管理します。共同墓地などに埋葬されるのが一般的です。
家庭裁判所から連絡が来る場合:相続財産管理人選任時など

相続手続きが進んでいる場合、特に相続人が不明な場合や相続財産を管理する必要がある場合、家庭裁判所から通知を受けることがあります。たとえば、相続財産管理人を選任する場合、相続手続きを進めるために裁判所から連絡が来ることがあります。
親族や知人から連絡が来る場合:連絡先を知っている場合のみ

親族や共通の知人が親の死を知っており、連絡先を把握している場合、連絡が来ることがあります。ただし、長期間音信不通の場合や現在の連絡先を誰も知らないケースでは、親族からの連絡がないこともあります。
連絡が来ない可能性が高いケース

疎遠な親が亡くなった場合、連絡が来ない可能性が高い状況もあります。
疎遠が長期間続いていた場合
親と長期間にわたって疎遠にしていた場合、連絡が来ない可能性があります。親に住所や連絡先を伝えておらず、親自身も周囲の人もあなたに連絡する手段がないケースは珍しくありません。身元確認や遺体の引き取りなどのための連絡であれば、あなたの兄弟姉妹やほかの親族に連絡がつけば、あなたには連絡が来ないかもしれません。
他の相続人が手続きを進めている場合
あなた以外の相続人が相続の手続きを進めている場合、連絡がこない可能性があります。本来、遺産分割の話し合いは相続人全員で行わなければならず、亡くなった方と疎遠だったことは連絡しなくてもいい理由にはなりません。しかし、親やほかの相続人と不仲だった場合には、連絡が来るのが遅れるか、まったく連絡が来ないケースもあります。また、ほかの相続人が相続放棄した場合、あなたに相続放棄した旨の通知をする義務はないので、何も連絡が来ないことも考えられます。
戸籍上の住所と実際の居住地が異なる場合
戸籍上の住所(住民票をおいている住所)と実際に住んでいる場所が異なる場合、相続手続きの際に相続人の住所確認作業が遅れ、通知が来ない場合があります。あなたが住民票の住所とまったく異なる場所に住んでいるとしたら、戸籍を取り寄せるなどして調べてもあなたの居場所を突き止めるのは困難です。場合によっては、行方不明者として扱われ、相続手続きが進められてしまうかもしれません。
親の死亡を知らなかった場合に直面するリスクと不利益

親の死亡を知らずに過ごしていた場合、気づいたときにはすでに相続に関する重要な手続きの期限が過ぎていたり、思わぬ不利益を被ったりする可能性があります。
相続放棄の期限(3ヵ月)を逃すリスク
相続には、プラスの財産(現金・不動産・有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・未払いの税金など)も含まれます。マイナスの財産が多い場合などには、相続の権利義務を全て放棄する「相続放棄」をする選択もあります。相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
借金や負債も引き継ぐことになる可能性

親が消費者金融や銀行から借金をしていた場合や、未払いの税金などがある場合、相続人が債務を引き継ぎます。特に、親が事業をしていた場合や保証人になっていた場合、多額の負債を抱えているケースも少なくありません。プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合は、相続人の負担になります。相続放棄の期限を過ぎると、たとえ借金の存在を知らなくても支払い義務が発生します。金融機関や債権者からの突然の督促に驚くことになるかもしれません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算される法的解釈
相続放棄の期限は 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内です。親が亡くなったことを知るのは亡くなった当日である場合が多いですが、疎遠だったためあとから親の死亡を知る場合や、亡くなった日がはっきりわからない場合もあります。そのため、相続放棄の期限は必ずしも被相続人が亡くなった日から3ヵ月以内ではありません。
親と疎遠にしていた場合は、家庭裁判所にきちんと事情を説明すれば、死亡から3ヵ月以上が経過していても相続放棄が認められる可能性があります。「親族から連絡が来て初めて知った」「役所から通知が届いて知った」など、何らかの形で情報を得た時点が基準になるとされるケースが多く、いつからカウントされるのかは個別の判断となります。
相続税の申告・納付期限を過ぎるリスク
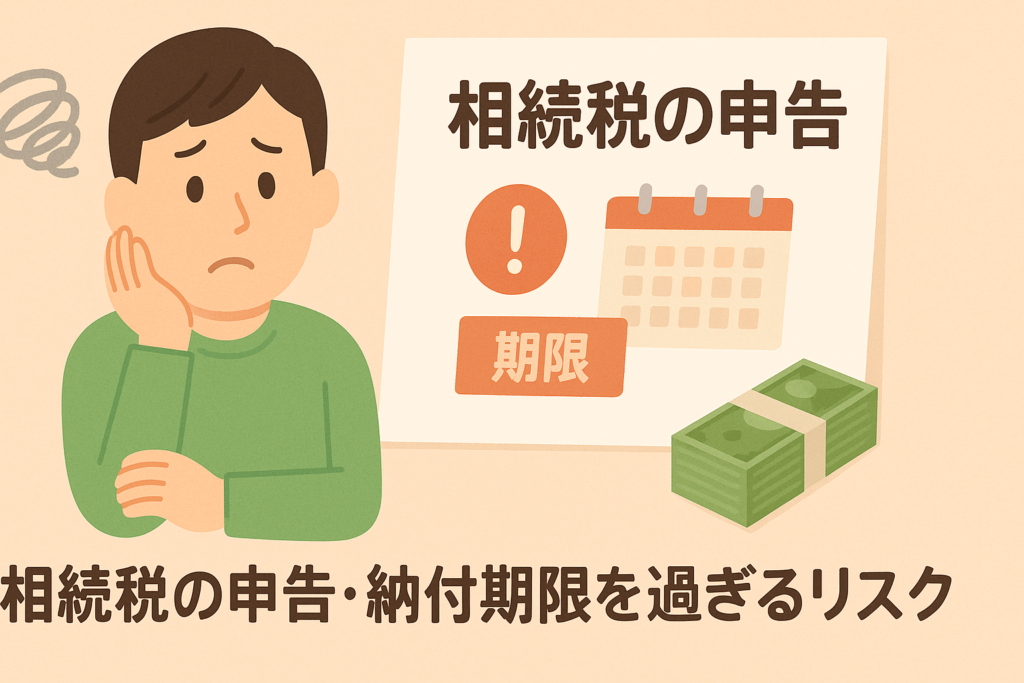
相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていると、相続税の申告と納付が必要になります。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。死亡の事実を知らなかった場合は申告期限が延長される可能性がありますが、何もしないでいるとペナルティを受けるおそれがあります。
延滞税や加算税が課される可能性
相続税の申告が遅れると納付も遅れるため、納期限の翌日から納付する日までの延滞税が発生します。また、故意ではなくても正当な理由なく申告しなかった場合は無申告加算税が課されることがあります。単に法律で期限が定められていることを知らなかったというのは申告が間に合わない理由として認められないため、親の死亡を知ったら早急に対応する必要があります。
無申告として税務調査の対象になるリスク
税務署では預貯金や不動産など個人の財産や取引に関する情報を蓄積しているため、相続税申告が必要となる対象者はある程度把握しています。そのため、相続税の申告を怠ると、税務署が調査に入る可能性があります。税務調査では、過去の取引履歴や口座情報が詳しく調べられ、不正と判断された場合にはより重いペナルティが課されることもあります。
不動産の名義変更が遅れるリスク

親が所有していた不動産を相続する場合、所有者の名義変更の登記をおこなう必要があります。しかし、親の死亡を知らなかった場合、登記が遅れて不利益を被る可能性があります。2024年4月から相続登記が義務化されたため、不動産の名義変更が遅れること自体にも罰金が発生するリスクがあります。
固定資産税の支払い問題
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。相続手続きの間は相続人の連帯債務となり、相続人の代表者が支払います。不動産の名義変更をしないままでは、相続人間で固定資産税の支払い義務が不明確になり、未納の状態が続くことがあります。未納が長期にわたると延滞金が発生し、最悪の場合、財産差し押さえのリスクも出てきます。
売却や活用ができない状態が続く問題
第三者に不動産の所有権を主張するには、登記が不可欠です。不動産の名義が亡くなった親のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。相続登記が完了するまでは、相続人全員が不動産の共有者となります。管理責任も共有となるため、意見の対立や費用の負担などでトラブルが生じる可能性があります。親の相続登記をする前に相続人のひとりが亡くなったり認知症になったりすると、手続きが煩雑になってしまうため、相続登記は早期に終わらせておくのが得策です。
知らないうちに遺産分割が進んでいるリスク
親の死亡を知らなかった場合、他の相続人がすでに遺産分割を進めている可能性があります。遺産分割協議に参加できなかった場合、法定相続分を確保できないリスクがあります。
法定相続分を確保できない可能性
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、疎遠だった相続人に連絡せず、ほかの相続人が勝手に手続きを進めてしまうことがあります。手続きを知らされないまま分配が終わってしまい、財産を受け取れない可能性もあります。
相続手続きのやり直しの労力と費用
相続人をひとりでも欠いた状態で行われた遺産分割協議は原則として無効です。しかし、一度行われた遺産分割協議を覆すことは難しく、裁判に発展することもあります。相続人がすでに財産を消費してしまった場合や第三者に譲渡してしまった場合、取り戻すのが困難です。弁護士を立てて労力と費用をかけて裁判で争っても、思いどおりに財産を受け取ることはできない可能性もあります。
親の死亡を自分から確認する方法
疎遠になっていた親が亡くなったかどうかは、基本的に自動で通知されることはありません。気になる場合は自分で確認する必要があります。ここでは、親の死亡を確かめるための具体的な方法について解説します。
戸籍謄本を取得して確認する具体的手順
親の死亡を確認する確実な方法のひとつは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得すること です。死亡届が提出されると、その情報が1週間から10日ほどで戸籍に反映されるため、数日前に亡くなった場合を除き、戸籍を確認することで死亡を確実に知ることができます。
本籍地がわかる場合の請求方法
本籍地がわかっている場合、親の本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得します。申請時に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。親の本籍地が遠方の場合は郵送で請求することも可能です。申請書、本人確認書類のコピー、返信用封筒(切手付き)、手数料(定額小為替など)を同封します。委任状を作成すれば、行政書士や家族などの代理人から請求することもできます。
本籍地がわからない場合の調べ方
親が住んでいた市区町村で住民票の除票を取得すると、住民登録がなくなった理由(転出・死亡など)とその日付がわかります。この書類から死亡の事実が判明する場合もあります。親が転出していて存命の可能性がある場合も、本籍地の記載があるため手がかりになります。ただし、住民票の除票の保存期間は住民登録がなくなってから5年間で、5年を過ぎると取得できません。
親の本籍地がわからない場合、自分の戸籍謄本を確認してみましょう。婚姻歴のある方は、親が筆頭者となっている結婚前の戸籍の本籍地を確認しましょう。戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得できます。ただし、婚姻により本籍地を別の市区町村に移した場合は、婚姻前の戸籍は元の本籍地の市区町村でしか取得できません。
親族や共通の知人に確認する際の注意点

親族や親の知人に連絡を取ることで、死亡の有無を確認できる場合があります。しかし、疎遠になっていた理由によっては、親族が情報を教えてくれないこともあります。突然の連絡が不審に思われる場合もあるため、慎重に話を進めることが大切です。「親と連絡が取れなくなったため、最近の状況を知りたい」といった聞き方をすると、協力してもらいやすくなります。
すでに相続の手続きが進んでいる場合、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性もあります。感情的にならず、冷静に状況を確認しましょう。
最後に住んでいた市区町村役所に問い合わせる方法
親が最後に住んでいた自治体の役所に問い合わせることで、死亡の事実を確認できる場合があります。しかし、単に「存命か亡くなったかを知りたい」という問い合わせには回答してもらえない可能性が高いでしょう。仮に親が亡くなっていたとしても、死亡届などの死亡時の手続きに関する書類も、特段の事情がなければ閲覧できません。先述のように、親の住民票の除票を取得することで、親の死亡や転出の状況を知るのがスムーズな方法でしょう。
専門家に調査を依頼する方法
自分で確認するのが難しい場合、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することで、法的に適切な方法で調査を進めることができます。あなたの委任があれば、戸籍謄本などを代理で取得することも可能です。すでに相続トラブルが発生している場合は、代理人としてあなたに代わって交渉できる弁護士に相談するのが適しています。ただし、費用が高額になる可能性があるため、まずは戸籍などの書類を取得して調査したい場合は行政書士に依頼するのがよいでしょう。
親の死亡を知った時点での適切な対応

親の死亡を知ったら、下記の内容を順番に確認する必要があります。内容によってはすぐに確認しなくてはいけないものもあるため、抜けがないようにしましょう。
すぐに確認すべき事項
親の死亡を知った際には、感情的な動揺があるかもしれませんが、速やかに確認すべき事項がいくつかあります。相続手続きには期限があり、放置すると思いもよらない不利益を被る可能性があるため、まずは冷静に状況を整理することが重要です。
死亡日と相続開始時期
親が亡くなった日付を正確に確認することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。相続は親の死亡と同時に発生し、相続人や相続財産の範囲も死亡日時点で決まります。各種手続きにも正確な死亡日が必要な場合が多いため、親の死亡日を戸籍謄本などの公式な記録で確認しましょう。
他の相続人の有無と連絡先
親が亡くなった際、相続人が自分一人であるとは限りません。自分のもうひとりの親や兄弟姉妹が相続人となる場合はわかりやすいですが、亡くなった親が再婚していたり認知している子がいたりすると相続関係が複雑になります。
相続人の範囲を正確に把握するには、親の出生から死亡までの戸籍を全てたどって確認する必要があります。特に、戸籍の本籍地が遠方だったり、過去に転籍を繰り返していたりすると、調査に時間がかかることもあります。
また、親族間で長年疎遠になっている場合や、まったく知らない人とともに相続人となるケースでは、相続人の現住所や連絡先を知るのが難しい場合もあります。相続人同士の連絡が遅れると、遺産分割協議の開始が遅れたり、知らないうちにほかの相続人が手続きを進めたりすることも考えられるため、早めに確認することが重要です。
相続財産の概要(プラスの財産・マイナスの財産)
相続の手続きを始める際には、親が遺した財産の内容を正しく把握する必要があります。財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金といった「マイナスの財産」も含まれます。プラスの財産が多ければ相続を選択するメリットがありますが、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討した方がよい場合もあります。
借金の存在は、通帳や督促状、信用情報の調査などから確認できます。親が他人の借金の保証人になっていた場合、保証債務も相続されることがあるため、細かくチェックすることが必要です。相続財産を総合的に判断し、相続するか相続放棄するかを決めましょう。
連絡経路別の初動対応

親の死亡を知る経路によって、必要な対応が異なります。それぞれのケースに応じた初動対応を理解し、適切に行動することが大切です。
警察から連絡が来た場合
警察から連絡があるのは、事件性が疑われる場合や、身元不明の状態で発見された場合、または親族がいないと判断されたケースです。まずは、警察に出向いて詳細を確認し、死亡の経緯や遺体の引き取りについて話を聞く必要があります。遺体の安置場所を確認し、必要であれば葬儀社に連絡して搬送の手配をします。また、遺品や所持品の受け取りについても確認しましょう。
役所から連絡が来た場合
市区町村の役所からの連絡は、孤独死や無縁仏となる可能性がある場合に行われることが多いです。役所は、法的な相続人を戸籍で調査したうえで、連絡を試みることがあります。この場合は遺体の引き取りについて確認しましょう。行政が火葬や埋葬を手配する場合は費用を請求される場合もあるため、負担の有無についても役所に問い合わせるとよいでしょう。
家庭裁判所から連絡が来た場合
家庭裁判所からの通知は、相続に関する手続きが開始された際に届くことがあります。たとえば、ほかの相続人が遺産分割調停を申し立てた場合や、相続財産管理人が選任された場合などです。この場合、裁判所の指示にしたがい、必要な書類を準備して対応する必要があります。相続を放棄する場合は期限内に家庭裁判所に申述することが求められます。
親族から連絡が来た場合
親族から直接連絡があった場合は、まず親が亡くなった状況や葬儀の有無について確認します。すでに葬儀が済み、遺産分割や相続手続きが進んでいる可能性もあるため、どのような状況なのかを把握することが重要です。子は親の法定相続人のため、原則として遺産分割協議に参加する権利がありますが、状況によっては円満に遺産分割協議を進めるのが難しいかもしれません。当事者同士の話し合いで解決しない場合は、調停など第三者に入ってもらって解決を図る方法もあります。トラブルに発展しそうな場合は弁護士に相談するのもひとつの手です。
相続する・しないの判断
親が亡くなった際、相続をするか放棄するかの判断が必要になります。相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の三つの選択肢があり、状況に応じた適切な判断が求められます。
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄は、親の財産や負債を一切引き継がない選択肢です。親に多額の借金があり、現金などのプラスの財産で返済しきれない場合は相続放棄を検討すべきです。自己のために相続の開始があったことを知った時(親の死亡を知った時)から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申し出る必要があり、期限を過ぎると借金も含めて相続することになるため迅速な判断が求められます。
限定承認という選択肢
限定承認は、親の財産と負債を精査し、プラスの財産の範囲内で負債を相続する方法です。これにより、親に借金があった場合でも、相続人が自己の財産から支払う必要はなくなります。相続財産の中に実家の土地建物などどうしても残したい財産がある場合、残せる可能性があるメリットがあります。ただし、相続人全員が共同で申請する必要があり、手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。限定承認の期限も、自己のために相続の開始があったことを知った時(親の死亡を知った時)から3ヵ月以内です。
単純承認のメリット・デメリット
単純承認とは、親の財産と負債を全て無条件で相続する方法です。特別な手続きは必要なく、相続放棄も限定承認もしなければ単純承認したことになります。大きな負債を全額引き継ぐリスクもあります。そのため、相続財産をしっかりと精査して決めることが重要です。
知らないうちに相続手続きが進んでいた場合の対処法

親の相続手続きが、自分の知らないうちに進んでいたことが判明した場合、腹立たしい気持ちも生まれるかもしれませんが、まずは現在の状況を把握することが先決です。遺産分割協議がすでに行われていた場合や、不正な遺産分割が疑われる場合など、状況に応じた適切な対応を取る必要があります。
遺産分割協議がすでに行われていた場合
相続人全員の合意が必要とされる遺産分割協議ですが、自分が知らないうちに他の相続人のみで話が進んでいた場合、無効を主張できる可能性があります。
無効主張できるケース
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加することが前提です。もし、あなたが相続人であるにもかかわらず何らかの事情で協議に参加していない場合、その協議は無効となる可能性があります。
具体的には、連絡がつかないためほかの相続人だけで話し合いを行った、不仲だったため意図的に連絡せずに手続きを進めてしまったというケースが考えられます。ただし、あなたを行方不明者として不在者財産管理人が代わりに協議に参加していた場合は、無効を主張できない可能性があります。
協議のやり直しを求める方法
無効を主張できる場合、まずはほかの相続人と話し合い、全員で協議のやり直しを求めるのが基本です。しかし、話し合いが難航する場合や、他の相続人が協議を拒否する場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、第三者である調停委員が双方の話を聞き、トラブルの解決を目指して調整をおこないます。
調停が成立しなければ、遺産分割の無効確認請求訴訟を提起する道もあります。相続人どうしで解決できない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
不正な遺産分割が疑われる場合の対応

遺産分割に不正が疑われる場合、状況を整理して法的手続きを進めましょう。不正の内容によって取るべき手段が異なり、相続人の権利を守るためには適切な証拠の収集と迅速な対応が求められます。
遺産分割無効確認訴訟
遺産分割協議が無効となる要因がある場合は、地方裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起できます。たとえば、自分が法定相続人であるにもかかわらず、協議に呼ばれずに進められていた場合は、その協議自体を無効とすることができます。遺産分割協議は、法定相続人全員の同意がなければ有効とは認められません。
また、相続人に認知症の方など意思能力を欠く人がいた場合や、未成年の子どもの特別代理人を選任しなかった場合も遺産分割協議の無効を主張できます。証拠として、過去の相続人間のやり取り、遺産の詳細なリスト、協議書の写しなどを準備しておくことが大切です。
遺留分侵害額請求権の行使
遺留分とは、被相続人の配偶者・子・親(直系尊属)に保証される最低限の相続分です。遺言や遺産分割協議によって特定の相続人が多くの財産を受け取るなど、公平性を欠くを遺産分割が行われた場合、多くの財産を受け取った相続人や遺贈を受けた人に遺留分を主張することが可能です。
遺留分を請求する際には、まず他の相続人に対して遺留分侵害額請求の意思を通知し、交渉を行います。話し合いが難航した場合は、調停や訴訟に移行します。なお、遺留分侵害額請求ができるのは、親の死亡および遺留分の侵害を知った時から1年(親の死亡を知らなかった場合は親の死亡から10年)以内です。
相続財産が処分されていた場合の対応
相続財産が、自分が知らない間に売却・譲渡・廃棄などの方法で処分されていた場合、不当利得返還請求や損害賠償請求によって取り戻せる場合があります。
不当利得返還請求
不当利得返還請求とは、法律的な原因に基づかずに得た利益の返還を求めることです。たとえば、ある相続人がほかの相続人に無断で相続財産である預貯金を引き出して使用した場合や、遺産分割協議の完了前に不動産を無断で利用して賃料収入を得ていた場合などがあります。
不当利得返還請求をおこなうには、不当利得の事実と返還を求める金額、期限などを記載した内容証明郵便を送付し、相手方と交渉して任意の返還を求めます。相手方が応じない場合は調停や訴訟によって解決を目指します。不当利得返還請求の時効は、権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間です。
損害賠償請求の可能性
相続財産が処分され、その結果としてあなたが経済的な損害を受けた場合、損害賠償請求ができます。相続財産である預貯金を引き出して使い込まれてしまったケースでは、不当利得返還請求と損害賠償請求のどちらを選ぶことも可能です。
損害賠償請求の時効は損害および加害者を知った時から3年と、不当利得返還請求と比べて短いため、時効の面で有利な不当利得返還請求を選ぶケースもあります。いずれにしても法的な知識が必要な手続きであることには変わりないため、弁護士に相談するのがよいでしょう。
相続手続き自体が不正に行われていた場合
遺言書が偽造された疑いがあるなど、相続手続き自体に不正が疑われる場合も、法的な対応方法があります。
相続欠格事由の確認
相続欠格とは、特定の重大な非行を行った相続人が、法律上相続権を失う制度です。遺言書を偽造または変造して自分に有利な内容にしたり、存在を隠したり、破棄したりするのは欠格事由です。また、被相続人をだましたり脅したりして遺言書を作成させることや、逆に被相続人が遺言書を作成するのを妨害することも欠格事由に該当します。
欠格となった相続人は最初から相続人でなかったことになります。相続欠格は、特別な手続きを経なくとも法律上当然に効果が生じるとされていますが、実際に相続欠格の効果を主張するためには欠格事由があることを証明する必要があります。相続欠格となる可能性のある行為が疑われる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
遺言書の有無と内容の確認方法
遺言書が存在するかどうかは、遺産分割の場面で非常に重要です。遺言がある場合は、遺言の内容が遺産分割協議よりも優先されます。親が遺言書を遺している可能性がある場合は、まずは徹底的に探しましょう。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されており、相続人は全国の公証役場で照会が可能です。亡くなった方の戸籍謄本とあなたの本人確認書類を持参して、最寄りの公証役場に問い合わせましょう。公証役場で遺言書の写しを取得すれば、内容も確認できます。
自筆証書遺言の場合、自宅のタンスや仏壇の引き出し、銀行の貸金庫などにしまってある可能性があります。自宅などで発見した遺言書に封がしてある場合は、勝手に開封してはいけません。相続人の立会いのもと、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認はその時点での遺言書の内容を確認するにとどまるため、偽造が疑われる場合は筆跡鑑定などを別途おこなう必要があります。
2020年以降、自筆証書遺言を本籍地の法務局で保管できるようになりました。自宅など身の回りで遺言書が見つからない場合は、親の本籍地の法務局にも問い合わせましょう。
まとめ:疎遠な親との関係でも知っておくべき相続の基本

事情があって疎遠な親でも、亡くなった際には無関係ではいられません。親が亡くなったことをすぐに知らせてもらえないことで、相続の手続きが煩雑になったり、ほかの相続人とのトラブルに発展したりする可能性があります。
普段から親族と良好な関係が築けるに越したことはありませんが、なかなか難しい場合もあるでしょう。その場合でも、もし親が亡くなったら誰が相続人になり、どのような手続きが必要なのかを事前に知っておくことはとても大切です。
親が亡くなっているかもしれないので調べたい、相続の手続きが自分抜きで進んでしまっているかもしれないなど、疎遠な親御さんの相続のことでお悩みの方は、ぜひ当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)にご相談ください。
相続の実績が豊富な行政書士があなたのお悩みを丁寧にお伺いし、解決いたします。必要に応じて提携している弁護士などの専門家におつなぎするため、安心してご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。










