相続手続きの費用は誰が払う?専門家別の費用分担、トラブル回避のポイントを解説
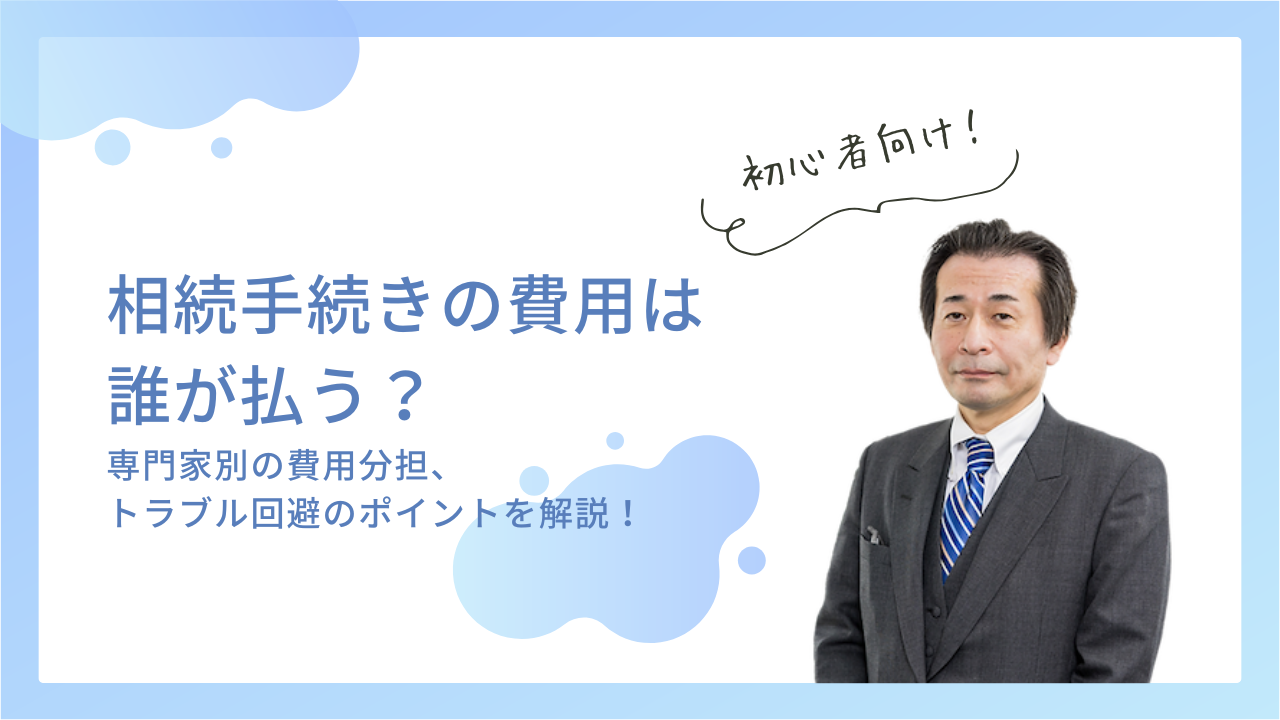
「相続手続きって、誰がいくら払うんだろう…」相続が発生すると、様々な費用がかかりますが、誰がどの費用を負担するのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続手続きの費用は、相続財産から負担するか、相続人全員で相続割合に応じて分担するのが一般的です。しかし、事前に費用の分担をきちんと決めておかないと、後々、相続人同士でトラブルに発展するケースも少なくありません。
この記事では、相続手続きの費用を誰がどのように負担すべきなのか、相続の状況別に詳しく解説します。さらに、「相続手続きにかかる費用の相場」や「トラブル回避のポイント」「費用が払えない場合の対処法」などもご紹介します。
この記事を読めば、相続費用の分担で迷うことなく、スムーズに相続手続きを進められるはずです。ぜひ参考にしてください。
【結論】相続手続きの費用は相続人全員が払うのが一般的

結論として相続手続きにかかる費用は、遺産から差し引くか、相続人全員が相続割合に応じて負担するのが一般的です。
相続手続き費用には、相続財産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議にかかる費用、遺言書の検認費用、不動産の名義変更費用、相続税の申告・納付費用、専門家への依頼費用などがあります。これらの費用は、遺産相続を公平かつ円滑に進めるために必要なものであり、相続人全員が公平に負担するのが基本的な考え方です。
しかし、相続手続き費用の負担について、事前に誰がどの費用を、どのように負担するのかをきちんと決めておかないと、後々、相続人同士でトラブルに発展する可能性もあります。例えば、相続人の一人が費用負担を拒否したり、費用分担の割合で意見が対立したりするケースがあります。
そのため、できるだけ早めに相続人同士で相談する場を設け、誰がどの費用を、どのように負担するのか、具体的な分担方法について話し合う必要があります。
相続手続きでかかる費用の種類と相場

ここでは相続手続きでかかる費用の種類と相場について、「相談料」「着手金」「報酬金」の項目に分けて紹介していきます。
相談料
遺産を相続する際、まずは専門家にどのように手続きを行っていくのかを相談しなければなりません。その際に発生する費用が「相談料」です。
相談料は相続人の状況によって、依頼するべき専門家が異なります。
- ▼例
- 相続人間で争いがある場合→弁護士
- 相続税の申告が必要な場合→税理士
- 不動産の名義変更が必要な場合→司法書士
- 主に書類作成を依頼したい場合→行政書士
そのため、次からは弁護士、税理士、司法書士、行政書士それぞれの相談料の相場、相談時間、相談可能な内容について解説していきます。
弁護士
弁護士への相談料の相場は、初回30分で5,000円から1万円程度が一般的で、初回相談を無料としている事務所も存在します。
相談時間は、30分から1時間程度の場合が多いです。
また弁護士に相談できる内容としては、下記のような法律的な問題全般が挙げられます。
- 遺産分割や遺留分の請求
- 相続放棄
- 遺言書の作成
特に、相続人同士の争いがある場合や、法的手続きを伴う問題が発生している場合に弁護士が力を発揮します。
税理士
税理士の相談料は、単発の相談で30分以内なら5,000円程度、1時間程度なら1万円ほどが相場です。事業者によっては無料相談をおこなうところもあります。
相談内容や事務所によりますが、相談時間は1時間程度が一般的です。
また税理士に相談できる内容は、下記のように税務に関するものが中心です。
- 相続税の申告や節税対策
- 相続財産の評価
- 税務署への対応など
相続税の申告が必要な場合や、税務に関する不明点がある際に税理士への相談が適しています。
司法書士
司法書士への相談料は事務所によって異なりますが、初回相談を無料とする場合も多く、一般的には30分あたり5,000円程度が相場です。
相談時間は多くの事務所で30分から1時間程度とされています。
また司法書士では、以下のような業務に対応することが一般的です。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の手続きなど
不動産登記や書類作成といった具体的な手続きが必要な場合には、司法書士への相談が有効です。
行政書士
行政書士の相談料は、1時間あたり3,000円から5,000円程度が相場であり、初回相談を無料としている事務所もあります。
相談時間は事務所によって異なりますが、30分から1時間程度であることが一般的です。
また行政書士に相談できる内容としては、下記のような書類作成や手続きのサポートなどが挙げられます。
- 遺産分割協議書や財産目録の作成
- 相続人や相続財産の調査
主に書類作成や手続きのサポートをおこなうため、相続に関する複雑な書類作成が必要な場合に行政書士が適しています。
着手金
相続手続きの相談を行ったあと、依頼をする際に「着手金」がかかるケースがあります。
着手金とは、専門家が業務を開始する際に依頼者が前払いする費用のこと。
多くの場合、着手金は返金されないため、契約時に費用や条件を確認しておくことが重要です。
次からは、各専門家に依頼した場合、どのくらいの着手金がかかるのか費用相場を紹介していきます。
弁護士
弁護士に相続関連の業務を依頼する際の着手金は、事案の複雑さや遺産の規模によって異なりますが、一般的には20〜30万円程度であることが多いです。
しかし相続人同士でトラブルが起きてしまい、調停が必要なケースは、着手金に50万円以上かかる場合もあるということを覚えておきましょう。
税理士
相続関連の業務を税理士に依頼する場合、事業所によって着手金を支払う場合とそうでない場合があります。
着手金を支払う場合の相場は、15万円〜30万円程度です。
着手金不要の税理士事務所は、業務が全て完了したあとに成果報酬を支払います。
依頼を検討する際には、各事務所の報酬体系や支払い条件を事前に確認し、自身の状況やニーズに合った事務所を選ぶことが重要です。
司法書士
司法書士に相続手続きを依頼する際も、事業所によって着手金が発生する場合とそうでない場合があります。
着手金が設定されている場合、通常は1万円〜10万円程度が相場です。
着手金が設定されていない事業者であっても、相続関係が複雑である場合は、請求されるケースもあるため事前の相談の際によく確認しておきましょう。
行政書士
行政書士に相続手続きを依頼する場合、着手金は1万円~5万円程度が相場で、総報酬額の一部として支払うことが一般的です。
ただし、事務所によっては着手金を不要とし、業務完了時にまとめて支払う形式を採用している場合もあります。
依頼前に見積もりを取り、報酬体系や支払い条件を十分に確認してから契約するのがおすすめです。
報酬
相続手続きを専門家に依頼する際は「報酬金」がかかることも覚えておきましょう。
報酬金とは、専門家が手続きの完了に向けて行った業務に対して支払う費用のことです。
この費用は、依頼内容の難易度や相続財産の規模、手続きの範囲によって変動します。
以下ではそれぞれの専門家へ支払う報酬金の相場費用を見ていきましょう。
弁護士
相続手続きにおける弁護士の成功報酬は、依頼者が受け取った経済的利益に応じて決まるということが一般的です。その報酬金の目安は以下のとおりです。
| 経済的利益の範囲 | 報酬金の目安 |
|---|---|
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
例えば弁護士のサポートによって1,000万円の経済的利益を得た場合、報酬金は10%の100万円に加えて18万円が加算され、合計で118万円の報酬額になります。
なお現在、報酬金の算出のしかたは、各事業者によって異なります。
そのため、依頼前には複数の弁護士事務所で相見積もりをとってから、契約するようにしましょう。
税理士
相続手続きにおける税理士の報酬は、主に「基本報酬」と「加算報酬」の二つに分けられます。
基本報酬は、相続財産の総額に応じて設定されることが一般的で、遺産総額の0.5%から1%が目安とされています。
| 相続財産の総額 | 税理士報酬の目安(0.5%〜1%) |
|---|---|
| 5,000万円 | 25万円〜50万円 |
| 1億円 | 50万円〜100万円 |
| 3億円 | 150万円〜300万円 |
| 5億円 | 250万円〜500万円 |
加算報酬は、相続人の人数や相続財産の内容、提供されるサービスの種類によって追加される費用です。
▼加算報酬の例
・相続人が複数いる場合
二人目以降の相続人一人ごとに基本報酬の10%から15%が加算
・非上場株式を相続する場合
一社につき15万円程度加算
これらの報酬体系は税理士事務所によって異なるため、依頼前の詳細な確認が重要です。
司法書士
相続手続きを司法書士に依頼する際の報酬相場は、依頼する業務の内容によって異なります。
以下に主な業務とその費用相場をまとめました。
| 業務内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 相続登記の代行 | 10万円~15万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 5万円~10万円程度 |
| 相続人調査 | 2万円~5万円程度 |
| 遺言書の作成支援 | 15万円~20万円程度 |
| 相続放棄の書類作成 | 5万円~8万円程度 |
司法書士事務所ごとに報酬体系やサービス内容が異なるため、複数の事務所で比較検討し、自分に合った事務所を選ぶことが重要です。
また、見積もりの段階で追加費用の有無を確認しておくと安心でしょう。
行政書士
相続手続きを行政書士に依頼する際の報酬相場は、業務内容によって異なります。
主な業務とその費用目安は以下のとおりです。
| 業務内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 遺言書の作成支援 | 6万円~10万円程度 |
| 相続人および相続財産の調査 | 5万円~6万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~5万円程度 |
| 預貯金や株式、車の名義変更 | 1件あたり2万円~5万円程度 |
依頼を検討する際は、複数の事務所に見積もりを依頼し、費用やサービス内容を比較することをおすすめします。
事前調査関連の手続き費用は誰が払う?

相続手続きを始めるにあたって、まず相続人や相続財産を特定するために必要な手続きを、この記事では「事前調査関連」の手続きと定義します。
ここでは相続を受ける前の「事前調査関連の手続き費用」を一般的に誰が払うのかを以下のケースに分けて解説していきます。
- 相続人や相続財産を調査する場合
- 遺言書の確認・執行をする場合
- 相続関係説明図を作成する場合
それぞれ見ていきましょう。
相続人や相続財産を調査する場合
誰が払う?
相続手続きを主導する相続人が支払い、最終的に相続人間での分担が一般的。
相続人や相続財産の調査は、被相続人が遺言を残していない場合や、家族関係が複雑で相続人を特定できないときに必要です。
たとえば、被相続人に過去の婚姻歴があり、その際に生まれた子どもがいる場合や、財産が多岐にわたり全容が不明な場合に行われます。
サポート内容は、戸籍謄本や住民票の収集、不動産や預貯金の調査を行い、相続人全員と財産の状況を特定します。
費用相場は、行政書士や司法書士に依頼する場合で5万円~10万円程度が一般的です。財産の種類や範囲が広い場合相続人の人数が多い場合や、調査が必要な財産が多岐にわたる場合には、追加費用が発生することもあります。
なお相続人や相続財産の調査では、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 戸籍収集や基本的な調査のみが必要な場合 | 行政書士 |
| 不動産調査や登記が必要な場合 | 司法書士 |
| 海外財産や税務問題が絡む場合 | 税理士や弁護士 |
遺言書の確認・執行をする場合
誰が払う?
遺言により財産を受け取る相続人や受遺者が負担する。もし遺言書に費用の負担者が指定されている場合は、その指示に従う。
ご家族が遺言書を残されていた場合、その内容を確認し、適切に執行する必要があります。この手続きを怠ると、遺言書の効力が認められないだけでなく、相続トラブルの原因にもなりかねません。
特に、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経なければ、法的に有効なものとして扱われません。この手続きでは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、内容を正式に確認します。
また、遺言書の内容が複雑で、財産の分配方法が分かりにくい場合や、相続人同士で意見が対立しそうな場合は、専門家へ相談することが望ましいです。専門家のサポートでは、遺言書の有効性を確認し、遺言の内容に基づいた財産分配の執行を行います。
費用相場は、遺産総額の1%から3%程度で、最低額として20万円〜50万円程度が設定されていることが多いです。
なお遺言書の確認・執行では、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 自筆証書遺言の検認手続きが必要な場合 | 行政書士や司法書士 |
| 遺言執行が必要で相続人間で争いが予想される場合 | 弁護士 |
| 公正証書遺言で単純な分配のみの場合 | 行政書士や司法書士 |
相続関係説明図を作成する場合
誰が払う?
相続手続きを進める代表者や相続財産管理者が負担。
相続手続きを進める中で、金融機関や法務局から、相続関係を証明する書類の提出を求められることがあります。その際に必要となるのが、相続関係説明図です。
相続人が複数いる場合や、金融機関から提示を求められた場合、法務局で不動産の名義変更手続きを行う場合に作成が必要です。
費用相場は行政書士や司法書士に依頼する場合で1万円~3万円程度が一般的ですが、相続人の人数が多い場合や、家族関係が複雑な場合には、追加費用が発生する場合もあります。
なお相続関係説明図を作成する場合は、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 単純な家族構成で基本的な説明図が必要な場合 | 行政書士 |
| 不動産や預貯金の相続割合計算が含まれる場合 | 司法書士 |
| 法的効力を重視する場合 | 弁護士 |
遺産分割関連の手続き費用は誰が払う?

ここでは以下のケースごとの手続き費用は、誰が払うべきなのかを解説していきます。
- 相続財産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議をサポートする場合
- 相続人同士でもめている場合
- 遺留分侵害額請求をする場合
それぞれ見ていきましょう。
遺産分割協議をサポートする場合
誰が払う?
相続手続きを主導する相続人が、一旦、費用の全額を立て替えて支払い、最終的には相続財産から差し引くか、相続人同士で、相続割合に応じて分担するのが一般的。
相続人間で遺産分割について話し合いが必要な場合に専門家に遺産分割協議のサポートを依頼します。特に、遺言がない場合や、相続人間で分割方法が明確でない場合に、このサポートを活用することが多いです。
専門家は、相続財産の全容を把握し、公平かつ法的に適切な分割案を作成します。また、遺産分割協議書の作成や、相続人全員が同意するための調整も行います。
費用相場は、行政書士や司法書士に依頼する場合で5万円〜10万円程度、弁護士に依頼する場合は相続財産の10%〜20%程度になることが一般的ですが、財産の種類や協議の複雑さによって変動します。
なお遺産分割協議のサポートを受ける場合、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 遺産分割協議書の作成のみ必要な場合 | 行政書士 |
| 不動産登記など追加手続きが必要な場合 | 司法書士 |
| 法的紛争の可能性がある場合 | 弁護士 |
なお、相続人全員が遺産分割の内容に合意しており、複雑な手続きが必要ない場合は、相続人だけで遺産分割協議を進めることも可能です。
ただし、専門家に依頼することで、よりスムーズかつ法的に間違いのない遺産分割協議を進めることができます。
遺産分割協議で揉めている場合
誰が払う?
法的手続きを主導する当事者が負担。ただし、最終的には調停や裁判で決定される場合もある。
遺産分割協議が難航し、相続人同士で意見が対立してしまった場合、調停や裁判といった法的手続きが必要になることがあります。そのような状況では、専門家のサポートを受けることが欠かせません。
弁護士は、相続人同士の意見が対立し、当事者間での話し合いが難しい場合に、代理人として交渉を行います。また、調停や裁判に必要な書類の作成や、裁判所での手続きも代行します。これにより、依頼者は精神的な負担を軽減し、法的に適切な解決を目指すことができます。
費用相場は、調停の場合で20万円〜50万円程度、裁判の場合で50万円〜100万円程度が一般的です。費用は事案の複雑さや遺産の規模によって異なります。
なお、遺産分割協議で揉めている場合は、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 調停や裁判で解決を目指す場合 | 弁護士 |
| 紛争が軽微で簡易な調整が必要な場合 | 行政書士や司法書士 |
遺留分侵害額請求をする場合
誰が払う?
遺留分侵害額を請求する側が費用を負担する。
遺言書の内容によって、本来相続できるはずの財産(遺留分※)が侵害された場合、遺留分侵害額請求という手続きを行うことで、ご自身の権利を主張することができます。
遺留分とは?
遺留分とは、法律で定められた相続人に最低限保障された相続財産の割合のことです。
遺言によって、特定の相続人に多くの財産が渡された場合でも、他の相続人は遺留分を請求することができます。
そのような場合、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士は、遺留分侵害額を正確に算出し、相手方に対して請求書を作成します。また、相手方との交渉や、調停、裁判になった場合でも、依頼者の代理人として対応します。
費用相場は、弁護士に依頼する場合で30万円〜100万円程度が目安です。案件の難易度や相続財産の規模によって増減することを覚えておきましょう。
不動産関連の手続き費用は誰が払う?

ここでは「不動産を相続する場合に必要な手続きの費用」を一般的に誰が払うのかを下記のケースに分けて解説していきます。
- 不動産の相続登記を依頼する場合
- 遺産相続の所有権移転登記をする場合
それぞれ見ていきましょう。
不動産の相続登記を依頼する場合
誰が払う?
相続手続きを主導する相続人が支払い、最終的には相続人全員での分担が一般的。
不動産の相続登記は、被相続人が所有していた不動産を相続人名義に変更するために必要です。
亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産を相続人の名義に変更する手続きが必要です。これを不動産の相続登記と言い、司法書士に依頼することが一般的です。
このサポートでは、司法書士が登記に必要な書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)の作成と提出を代行します。また、不動産の固定資産税評価額に基づく登録免許税の計算や納付手続きも行われます。
費用相場は、司法書士への報酬として5万円~10万円程度が一般的です。また、実費として不動産の登記手続きを行う際に国に納める税金である登録免許税が不動産の評価額の0.4%が必要です。
遺産相続の所有権移転登記をする場合
誰が払う?
相続人間で協議を行い、最終的に不動産を取得する相続人が負担するのが一般的。
遺産分割協議の結果、不動産を相続することになった場合、その不動産を正式に相続人の名義に変更する手続きが必要です。これを所有権移転登記といい、司法書士に依頼することが一般的です。
特に、不動産を売却したり、第三者に貸し出したりする場合には、登記名義人が誰であるかが重要になります。登記が完了していないと、売買契約や賃貸契約をスムーズに進めることができません。
そのため司法書士では、登記に必要な書類の作成と法務局への提出を代行します。また、登記完了後に必要書類の返却や名義変更に伴う行政手続きのサポートも行われます。
費用相場は、司法書士への報酬が5万円~15万円程度、登録免許税が不動産評価額の0.4%必要です。さらに、複数の不動産を所有している場合や手続きが複雑な場合は、追加費用が発生する場合があります。
税金関連の手続き費用は誰が払う?

ここでは相続税の対象となった場合「税金関連の手続き費用」を一般的にだれが払うのかを下記のケースに分けて紹介していきます。
- 相続税の申告と納付をする場合
- 税務調査対応を依頼する場合
- 二次相続対策を依頼する場合
それぞれ見ていきましょう
相続税の申告と納付をする場合
誰が払う?
相続税を納める相続人が費用を負担。
相続税の申告と納付は、相続財産が基礎控除額を超える場合に行う必要があります。
基礎控除額とは、相続税が課税されない最低限の財産額のことで、相続人の数や家族構成によって計算方法が異なります。
この手続きを怠ると、延滞税や加算税が課される可能性があるため注意しましょう。
▼延滞税課された事例
- 相続税の納付期限(相続開始から10ヶ月以内)を過ぎてしまった
- 納税資金の準備が間に合わず、期限後に支払った
- 申告が遅れたことに気づいたが、そのまま放置してしまった
▼加算税が課された事例
- 申告漏れや計算ミスにより申告額が少なすぎた
- 図的に財産を隠したり、虚偽の申告をした
そのため相続税の申告と納付は、税理士に依頼するのが一般的です。
サポート内容としては、相続財産の評価、控除の適用、相続税申告書の作成などの代行を行います。また、納税方法や節税対策についてのアドバイスを行ってくれる場合もあります。
費用相場は、遺産総額の0.5%~1%程度が一般的で、最低費用として20万円~50万円程度が設定されている場合もあります。
税務調査対応を依頼する場合
誰が払う?
基本的に調査対象となった相続人が費用を負担するが、相続税の修正が必要になった場合には、他の相続人もその修正内容に応じて費用を負担する場合もある。
税務調査対応は、税務署で申告内容に不備があると判断された場合や高額な遺産がある場合に必要です。
税務署から税務調査の通知が来た場合、税理士に相談せずに対応してしまうと、税務署からの指摘を正しく理解できなかったり、税務署の質問に適切に答えられず、本来よりも多くの税金を支払うことになってしまう可能性があります。税務調査に適切に対応するためにも、税理士に依頼するのが安心です。
税務調査対応では、税務調査への立ち合い、調査内容の説明、税務署との交渉を代行します。また、指摘事項に対する反論や修正申告の作成も行います。
費用相場は、20万円~50万円程度が一般的です。事案の規模や調査内容によって増減する場合もあります。
二次相続対策を依頼する場合
誰が払う?
次の相続を見据えて財産管理をおこなう相続人が費用を負担。
二次相続対策は、夫婦間での一次相続後に発生する次の相続に備えるための対策です。
たとえば、ご夫婦のどちらかが亡くなられた後(一次相続)、残された配偶者の方の相続(二次相続)についても、事前に準備しておくことが大切です。
二次相続とは、夫婦のどちらかが亡くなられた後、残された配偶者が亡くなられた際に発生する相続のことです。
一次相続で配偶者が多くの財産を相続した場合、二次相続では、その財産も相続税の課税対象となるため、税負担が大きくなる可能性があり適切な対策が必要になります。
二次相続で高額な相続税が発生するリスクを抑えるためには、遺産分割方法の工夫や生前贈与の活用など、様々な対策を講じる必要があります。
税理士は、一次相続後の財産状況を踏まえ、二次相続で発生する相続税を試算し、遺産分割方法や生前贈与の活用など、相続税を抑えるための最適なプランを提案します。また、相続税のシミュレーションを通じて、具体的な税負担を見える化します。
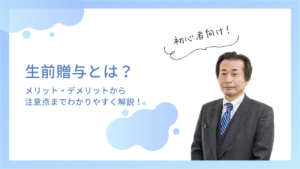
費用相場は、30万円~100万円程度で、提案内容や対策の複雑さによって異なります。
なお二次相続対策を依頼する場合、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 簡単な財産分割と節税対策が必要な場合 | 税理士 |
| 複雑な財産管理や贈与計画が必要な場合 | 税理士 |
| 法的な争いが予想される場合 | 弁護士 |
イレギュラーな手続きが発生した場合の費用は誰が払う?

ここでは相続に関して「イレギュラーな手続きが発生した場合の費用」を一般的にだれが払うのかを見ていきましょう。
- 相続放棄や限定承認をする場合
- 相続財産管理人を依頼する場合
それぞれ紹介していきます。
相続放棄や限定承認をする場合
誰が払う?
相続放棄や限定承認をする相続人が費用を負担する。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しない手続きのことです。
一方、限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、借金などの債務を弁済する手続きのことです。
相続放棄は、相続人としての地位を失うことになりますが、限定承認は、相続人の地位を維持しながら、責任を限定することができます
たとえば、被相続人が多額の借金を抱えていた場合や、事業を行っていて、負債の方が資産よりも多い場合などや、相続財産の中に価値が不明確なものが含まれている場合、相続人は相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
サポート内容としては、家庭裁判所への申述書の作成や提出代行などが挙げられます。また、限定承認の場合は、相続財産の目録作成や債務整理も含まれます。
費用相場は、司法書士や弁護士に依頼する場合、相続放棄で1件あたり3万円~5万円程度、限定承認で10万円~30万円程度が一般的です。限定承認は手続きが複雑なため、費用が高額になる傾向があります。
なお相続放棄や限定承認をする場合、状況に応じて下記の専門家に依頼するのがおすすめです。
| 状況 | 適切な専門家 |
|---|---|
| 相続放棄を単独でおこなう場合 | 司法書士または弁護士 |
| 限定承認が必要で財産目録の作成が必要な場合 | 弁護士 |
| 複数の相続人が一括して手続きをおこなう場合 | 弁護士 |
相続財産管理人の費用は相続財産から払う
誰が払う?
相続財産管理人の費用は原則として相続財産から支払われます。
相続が発生したものの、相続人が誰もおらず、遺産を管理する人がいない場合があります。このような場合に、家庭裁判所によって選任されるのが相続財産管理人です。
この手続きは、残された財産を適切に処理し、債権者や利害関係者に公平に分配するために行われます。たとえば、被相続人が一人暮らしで身寄りがない場合や、相続人が全員相続放棄した場合などが、相続人が不在または不明な場合に該当します。
サポート内容は、相続財産の調査、売却手続き、債務弁済、残余財産の分配などが挙げられます。家庭裁判所が管理人を選任し、弁護士がその役割を担うことが一般的です。
費用相場は、管理人の報酬が20万円~50万円程度で、財産の規模や内容によって増減します。この報酬は原則として相続財産から支払われますが、財産が不足している場合は関係者が負担する可能性もあります。
相続手続きの費用を誰が払うかトラブルにならないためのポイント

相続手続きは、様々な費用が発生するため、相続人間で誰がいくら負担するのかを事前に決めておかないと、後々トラブルになる可能性があります。そこで、この章では、費用トラブルを未然に防ぐためのポイントを解説します。
- 手続き費用にいくらかかるか見積もりを取っておく
- 各相続人の負担割合を事前に取り決めておく
- 代表者が立替える場合は領収書を保存しておく
- 必要に応じて専門家に相談する
それぞれ詳しく解説していきます。
手続き費用にいくらかかるか見積もりを取っておく
相続手続きの費用負担でトラブルを防ぐためには、事前に手続き費用の見積もりを取得するのが重要です。
専門家に電話やメールで問い合わせをするほか、直接事務所に訪問するなどした上で見積もりを依頼し、内訳や総額を確認すれば費用を明確に把握できます。
見積もりを確認する際には、基本料金に含まれる手続きの範囲、追加費用が発生する可能性、キャンセル料の有無などを確認しましょう。
また、各専門家に支払う報酬と手続きを進めるためにかかる実費(例:登録免許税や戸籍謄本・住民票の取得費用、印紙代など)の区別を把握し、複数の専門家から見積もりを比較すれば、納得できる費用負担を決めやすいです。
事前に見積もりを取得し、内容をしっかりと確認することで、予期せぬ費用トラブルを回避できるだけでなく、予算に合わせた相続手続きを進められるでしょう。
各相続人の負担割合を事前に取り決めておく
相続手続きでは、誰がいくら費用を負担するのかが曖昧なまま手続きを進めてしまうと、後々トラブルの原因になることがあります。この章では、費用負担の割合を事前に決めておくことの重要性と、具体的な方法について解説します。
負担割合を決める際には、相続人間の話し合いで合意を形成し、必要であればその内容を文書化しておくとよいでしょう。
費用分担の方法としては、「相続財産に応じた分担」「頭割りで均等に分担」「遺産から費用を差し引いて分配」といったケースが一般的です。
以下ではそれぞれのケースについて、具体例を挙げて説明していきます。
ケース1:相続財産に応じた分担
相続財産に応じた分担は、遺産分割協議の結果、各相続人の取得割合が大きく異なる場合に有効な方法です。
遺産を多く相続する人が、その分、費用も多く負担するというように、相続財産の取得割合に応じて、手続き費用を分担します。
このケースでは、遺産を多く取得する人が相応に多くの費用を負担するため、公平性が確保されやすいといえるでしょう。
▼例
遺産総額が2,000万円で、相続人Aが1,200万円、Bが800万円を相続する場合、手続き費用が20万円発生したとします。この場合、Aが12万円(60%)、Bが8万円(40%)を負担します。
ケース2:頭割りで均等に分担
頭割りで均等に分担は、遺産分割の割合にかかわらず、相続人全員が均等に費用を負担する方法です。この方法は、手続きがシンプルなので、相続人間の負担割合を公平にしたい場合におすすめです。
▼例
相続人A、B、Cの3人が均等に手続き費用を負担する場合、20万円の費用が発生した場合、それぞれが6万6,666円(1/3)ずつ負担します。
ケース3:遺産から費用を差し引いて分配
遺産から費用を差し引いて分配する方法は、相続人間で費用の分担について個別に話し合う手間を省き、手続きをシンプルにしたい場合に有効です。
この方法は、費用負担の割合で揉める可能性を低くすることができます。
▼例
遺産総額が1,000万円で、手続き費用が20万円発生した場合、遺産から費用を差し引いた980万円を相続人間で分配します。AとBがそれぞれ50%ずつ相続する場合、それぞれ490万円を受けとることになります。
代表者が立替える場合は領収書を保存しておく
相続手続きで代表者が費用を立て替える際には、領収書を必ず保存するようにしましょう。
領収書を適切に保管しておくことで、ほかの相続人に支出内容を説明しやすくなり、不必要なトラブルを防ぐことができます。
また領収書には、支払い内容だけでなく、いつ、誰に、どのような目的で支払ったのかを具体的に記載しておきましょう。例えば、「〇〇行政書士事務所 相続登記費用」のように、具体的に記載しておくことで、後から確認する際に内容が分かりやすくなります。
さらに紙の領収書は紛失のリスクがあるため、スマートフォンで撮影したりスキャンしたりして、デジタルデータとして保存するようにしましょう。
データ化しておけば、ほかの相続人と簡単に共有でき、透明性を保つことができます。
必要に応じて専門家に相談する
相続手続きの費用負担をどうするか決めたい場合、状況に応じて専門家に相談するのも良いでしょう。
もし相続人間で意見が対立している場合は、弁護士に相談するのが最適です。弁護士は法律の観点から公平な分担方法を提案し、必要であれば調停や法的な合意書の作成をサポートしてくれます。
全員が費用負担について合意している場合は、公証人役場で合意内容を公正証書として文書化するのが良いでしょう。これにより、合意内容が公的に証明され、のちのトラブルを防ぐことができます。
意見が対立していないものの、話し合いが進まない場合には、司法書士や行政書士が第三者として中立的に話し合いを進める方法も効果的です。第三者の進行役がいることで、冷静かつ建設的な議論が可能です。
このように状況に応じて専門家を活用することで、相続手続きの費用負担についての不安やトラブルを軽減し、スムーズに解決する道筋をつけられるというメリットがあります。
状況に応じた適切な相談先を選び、専門家の知識や経験を上手に活用しましょう。
相続手続きの費用を払えないときの対処法

相続手続きを進めたくても、費用が足りないという状況に直面することもあるでしょう。そこで、この章では、相続手続きの費用を払えない場合の対処法について解説します。
相続手続きの費用を払えない場合、以下の方法を行ってみましょう。
- 遺産から費用を捻出する
- 分割払いを交渉する
- 法テラスの民事法律扶助を利用する
- 親族に援助を求める
- 不要な財産を売却する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺産から費用を捻出する
相続手続きの費用を払えない場合、遺産を相続手続き費用に充てることを検討しましょう。
たとえば、現金や預貯金が遺産の中に含まれている場合、それを利用して手続き費用を支払います。また、遺産分割協議書を作成する際に、全員の合意を得て費用を遺産から差し引く形にすれば、公平に費用負担ができます。
ただし、遺産は相続人全員の共有財産となるため、遺産を費用に充てるためには、相続人全員の同意が必要となります。もし、相続人のうち一人でも同意しない場合は、遺産から費用を捻出することはできません。
特に不動産などの現物資産は、現金や預貯金と異なり、すぐに費用に充てることができません。売却には不動産鑑定、売買契約、登記手続きなどが必要となるため、相続人全員で事前に協議し、売却を進めるかどうかを決める必要があります。
分割払いを交渉する
司法書士や税理士、弁護士などの専門家に依頼する場合、分割払いに対応してくれる場合もあります。 まとまった費用一括で用意するのが難しい場合に検討してみましょう。
なお、分割払いの交渉時には、支払いスケジュールを明確にし、契約書などを交わすことが大切です。信頼関係を保ちながら無理のない支払い計画を立てましょう。
法テラスの民事法律扶助を利用する
相続手続きの費用を支払う余裕がないという方のために、国が運営する法テラスの「民事法律扶助制度」という制度があります。この制度を利用すれば、弁護士費用や司法書士費用を立て替えてもらうことが可能です。立て替えられた費用は、無利子での分割返済が可能です。
ただし「民事法律扶助制度」の利用には以下の条件があるので、注意が必要です。
- 収入や資産が基準を満たす必要がある
- 法テラスで紹介された専門家を利用する
具体的な基準は、法テラスの公式サイトで確認することができます。事前に問い合わせを行い、必要な書類を準備しましょう。
親族に援助を求める
相続手続きの費用が不足している場合は、親族に援助を求めることも、一つの選択肢です。相続は、家族全員に関わることですので、親族間の協力によって、費用を工面できる可能性があります。
親族に援助を依頼する際には、具体的な費用の内訳と総額を伝え、何にいくら必要なのかを明確に説明しましょう。また、返済スケジュールについては、いつまでに、いくらずつ返済するのかを、具体的に提示し、親族の理解を得ることが大切です。
不要な財産を売却する
相続手続きの費用を工面するために、相続財産の中に不要なものがあれば、売却を検討することも有効な手段です。売却によって得たお金を、手続き費用に充てることができます。
たとえば、使う予定のない不動産や車、株式などを売却し、その代金を手続き費用に充てます。遺産の一部を売却して得たお金で、相続手続きの費用を賄うことができれば、相続人全員で費用を分担する必要がなくなるため、手続きがスムーズに進むことがあります。
不動産や高額な資産を売却する場合は、相続人全員の同意が必要です。また、不動産や株式などの資産は、市場価格が変動するため、売却のタイミングによっては、損をしてしまう可能性があります。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に売却を進めることをおすすめします。
まとめ
この記事では、相続手続きの種類によって、誰が費用を負担するのか、費用相場はどれくらいなのかを解説してきました。
最後に、この記事で解説した内容を一覧表にまとめました。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせて、確認してみてください。
| ケース | 誰が費用を負担するのか | 費用相場 | |
|---|---|---|---|
| 事前調査関連の手続き | 相続人や相続財産を調査する場合 | 相続手続きを主導する相続人が負担し、最終的に分担 | 5万円~10万円(行政書士・司法書士) |
| 遺言書の確認・執行をする場合 | 遺言で財産を受けとる相続人や受遺者 | 遺産総額の1~3%(20万円~50万円以上) | |
| 相続関係説明図を作成する場合 | 手続きを進める代表者または財産管理者 | 1万円~3万円(行政書士・司法書士) | |
| 遺産分割関連の手続き | 遺産分割協議をサポートする場合 | 主導する相続人が負担し、最終的に分担 | 5万円~10万円(行政書士・司法書士)、財産の10~20%(弁護士) |
| 遺産分割協議で揉めている場合 | 法的手続きを主導する当事者が負担 | 調停:20万円~50万円、裁判:50万円~100万円 | |
| 遺留分侵害額請求をする場合 | 請求する相続人が負担 | 30万円~100万円(弁護士) | |
| 不動産関連の手続き | 不動産の相続登記を依頼する場合 | 主導する相続人が負担し、最終的に分担 | 5万円~10万円(司法書士)、登録免許税:評価額の0.4% |
| 遺産相続の所有権移転登記をする場合 | 不動産を取得する相続人が負担 | 5万円~15万円(司法書士)、登録免許税:評価額の0.4% | |
| 税金関連の手続き | 相続税の申告と納付をする場合 | 相続税を納める相続人が負担 | 遺産総額の0.5~1%(20万円~50万円以上) |
| 税務調査対応を依頼する場合 | 調査対象の相続人が負担 | 20万円~50万円(税理士) | |
| 二次相続対策を依頼する場合 | 財産管理をおこなう相続人が負担 | 30万円~100万円(税理士・弁護士) | |
| イレギュラーな手続き | 相続放棄や限定承認をする場合 | 放棄・限定承認をする相続人が負担 | 相続放棄:3万円~5万円、限定承認:10万円~30万円 |
| 相続財産管理人を依頼する場合 | 原則、相続財産から支払われる | 20万円~50万円(弁護士) |
※上記はあくまで一般的な目安です。実際の費用は、専門家や手続きの内容、相続財産の規模などによって変動する場合があります。
一般的には、上記の表のように費用負担する場合が多いですが、そもそもトラブルにならないよう、事前に相続人同士で費用負担について話し合うのが大切です。
もし、相続手続きの費用負担について、相続人間で話し合っても結論が出ない場合や、意見が対立してしまった場合は、一人で悩まず、専門家に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。
相続手続きのことなら行政書士佐藤秀樹事務所へ
当事務所「行政書士佐藤秀樹事務所」では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な相続手続きをご提案いたします。
当事務所は弁護士、税理士、司法書士とも提携しております。そのため、お客様は複数の専門家を探す手間を省き、ワンストップで相続に関するあらゆるお悩みを解決することが可能です。
- 相続手続き全般のサポート:遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、各種書類作成など、相続手続きに必要なサポートをいたします。
- 他士業との連携:相続税の申告、不動産の登記、相続トラブルの解決など、必要に応じて、提携の専門家をご紹介し、トータルでサポートいたします。
- 初回無料相談:相続に関するご相談は、初回無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。
相続手続きに関するお悩みは、ぜひ当事務所にお任せください。










