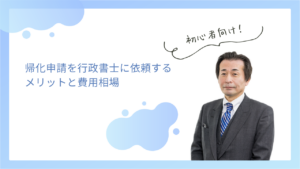在留期間更新許可申請書の書き方と準備するべき書類を解説
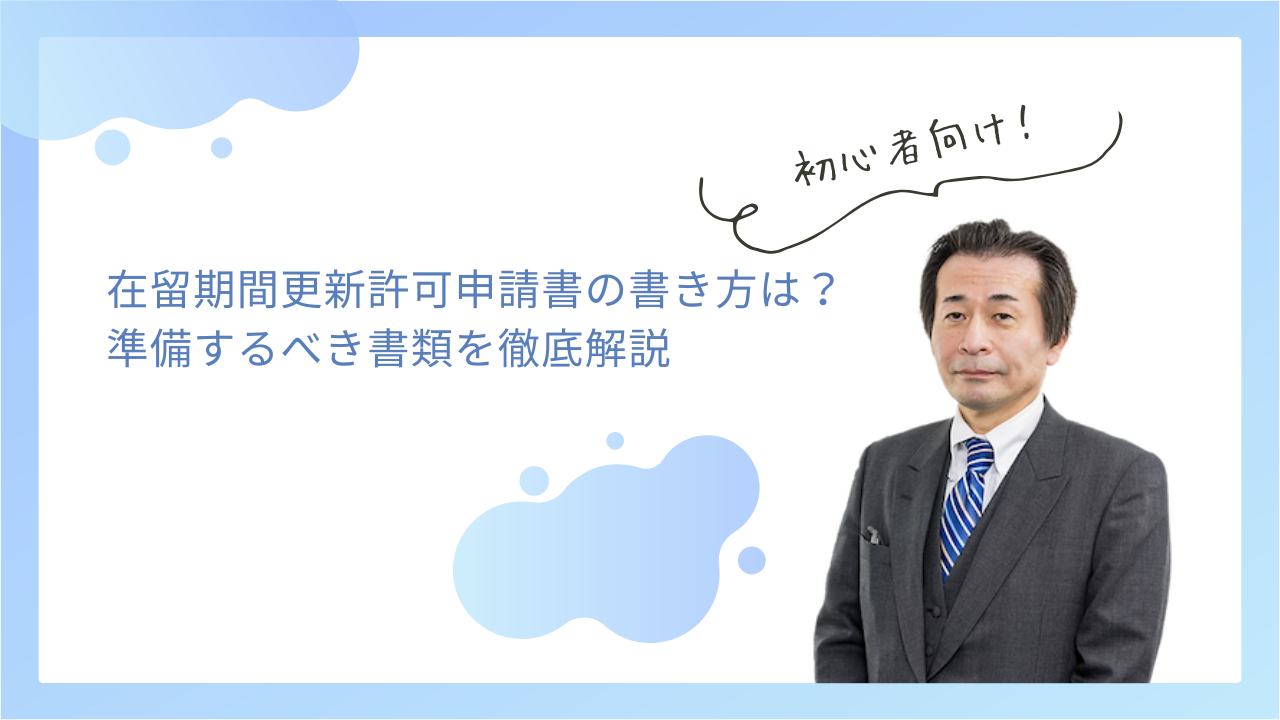
在留期限が近づき、更新許可申請に不安を感じていませんか?初めて更新する方や、離婚や転職でビザ取得時と事情が変わった方は、特に大きな不安を抱えていることでしょう。
本記事では、在留期間更新許可申請書の記入ポイント、必要書類とその取得方法、そして不許可を防ぐための具体的な対策について、専門家がわかりやすく解説します。ぜひ、スムーズに申請を進めるための参考にしてください。
在留期間更新許可申請の基本
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格を維持したまま、引き続き日本に滞在するための重要な手続きです。手続きを怠ると最終的には帰国させられてしまうおそれがあるため、在留期限が迫る前に計画的に準備を進める必要があります。申請書以外にも多くの添付書類があるため、書類不備が原因で審査が遅れることがないよう、手続きの基本を押さえましょう。
準備開始のタイミングは3ヶ月前
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する日の3ヶ月前から可能です。審査には通常、数週間から1ヶ月程度かかるため、早めに申請しておくことで、在留期限が切れる前に新しい在留カードを受け取れる可能性が高くなります。
年末年始や夏季休暇など、出入国在留管理局が混み合う時期を挟むと審査期間が長くなる傾向があります。期限ギリギリでの申請は、書類に不備が見つかった場合に対応する時間がありません。余裕をもって3ヶ月前から準備を始め、遅くとも在留期間満了の1ヶ月前までには申請を済ませるスケジュールがおすすめです。
現在の在留期間が短期の場合は、在留期間の半分が経過した日から申請が可能です。在留期限を確認して早めに対応しましょう。
もし審査中に在留期限が切れても大丈夫!「特例期間」とは?
万が一、在留期間が満了する日までに審査が終わらず、新しい在留カードを受け取れなかった場合でも、焦る必要はありません。申請期間中の特例として、現在の在留期間が満了したあとも、申請の結果が出るまで引き続き日本に滞在することを認める特例期間の制度があります。
特例期間は、申請が受理された時点から審査結果が出るまでの期間、または在留期間が満了した日から2ヶ月間のいずれか早い日まで適用されます。申請さえ期限内に行っていれば、審査期間が長引いてもオーバーステイになる心配はありません。
ただし、在留期間更新許可申請が適法に行われていることが前提です。書類に重大な不備があったり、申請自体が却下されたりした場合は適用されないため、申請書類の準備は入念におこないましょう。特例期間中も現在の在留資格に基づく活動しかおこなえない点にも注意が必要です。
うっかり更新を忘れたらどうなる?オーバーステイのリスクと対処法
在留期間更新許可申請をうっかり忘れて在留期間を過ぎると、「オーバーステイ(不法残留)」という重大な法令違反となります。オーバーステイは退去強制や一定期間日本への再入国が不可能になるなど、非常に重い罰則の対象です。
万が一、在留期間を過ぎてしまったことに気づいたら、すぐに出入国在留管理局に行って事情を説明しましょう。病気で入院していたなどやむを得ない事情がある場合は、事情を証明できる書類を準備して正直に説明しましょう。「忘れていた」「忙しかった」という理由は正当な理由として認められません。
オーバーステイしてしまうと通常の在留期間更新申請はできず、「在留特別許可」を求めることになります。難易度が高い手続きであり、許可される保証はありません。 自分で何とかしようと行動するのはリスクが大きいため、一刻も早く行政書士や弁護士などの専門家に相談し、今後の対応についてのアドバイスを受けましょう。
在留期間更新許可申請書の記入例と注意点
在留期間更新申請書は必ず提出が必要な書類です。出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードできます。在留資格によって様式が異なるため、必ずあなたの在留資格の様式を使用しましょう。ここでは、申請書の記入のポイントを解説します。
申請書1枚目の記入ポイント
在留資格が異なっても申請書の1枚目には共通する項目が多く、大部分が申請者の基本情報と現在の在留情報の記載欄です。以下の点に注意しながら正確に記載しましょう。
| 項目 | 記入のポイントと注意点 |
| 個人情報(氏名、生年月日、国籍など) | パスポートや在留カードの記載と一致させる必要があります。 |
| 写真貼付欄 | サイズは縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したものを使用します。正面を向き、帽子は被らず、背景のない鮮明な写真を選び、はがれてしまった場合に備えて裏面に名前を書いておきましょう。 |
| 在留情報(在留資格、在留期間満了日など) | 在留カードの記載と一致させ、現在の在留期間満了日を確認して正確に記入します。 |
| 希望する在留期間 | あなたの希望する期間(3年、5年など)を記入します。希望通りに許可されるとは限りませんが、正直な希望を書きましょう。 |
| マイナンバー(個人番号) | 記載は任意です。記載するとデータ照合がスムーズになる可能性があるため推奨しますが、書かなくても審査には問題ありません。 |
パスポートや在留カードを確認しながら正確に記載することを心がけましょう。
記入のポイント|技術・人文知識・国際業務の場合
就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の更新申請書では、雇用・職務の継続性と安定した生活を証明する点が重要です。
現在の所属機関(勤務先)の名称や所在地、雇用期間などの基本情報を正確に記入します。更新の理由は「現在のAプロジェクトに引き続き従事するため」など、具体的に書くとよいでしょう。所属機関や活動内容の詳細は、勤務先に記載してもらいます。活動内容は専門性が伝わるように簡潔に記述します(例:IT部門におけるシステム設計業務)。誰でもできる単純作業と誤認されるような記述は避けましょう。
記入のポイント|日本人等の配偶者の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の更新申請書では、婚姻の継続性・真実性と世帯の経済的基盤を証明する点が重要です。
在日親族の欄には配偶者である日本人の氏名や住所などを正確に記入します。滞在費支弁方法の欄では、収入源(例:配偶者の収入・貯金)と毎月の平均支弁額を記入します。年間所得(年収)については、申請人および配偶者の直近の年収額を記入します。更新が必要な理由は「夫婦として安定した家庭生活を継続していくため」など、婚姻の継続意思を明確に記しましょう。
在留資格更新許可申請の必要書類と取得方法
在留資格更新許可申請に必要な書類は多岐にわたり、書類の不備で審査に時間がかかるケースも少なくありません。事前に準備する書類を把握し、申請に向けて早めに準備しましょう。
全員必ず準備するものの筆頭は「在留期間更新許可申請書」です。前述のとおり、在留資格によって使用する様式が異なるため注意が必要です。パスポートと在留カードは申請時に提示するため、必ず携帯しましょう。また、世帯全員が載っている住民票(発行から3ヶ月以内のもの)も準備します。
その他に、在留資格ごとに添付書類が必要です。ここでは、「技術・人文知識・国際業務」と「日本人等の配偶者」の添付書類の例を紹介します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の添付書類例
| 添付書類 | 備考 | 取得先 |
| 住民税の課税証明書及び納税証明書 | 直近1年分。世帯主のものも必要となる場合があります。 | 市区町村役場 |
| 在職証明書 | 現在の所属機関から発行してもらいます。 | 所属機関 |
| 所属機関の概要を示す書類 | 四季報の写し、会社の案内、登記事項証明書、直近の決算文書の写しなど | 所属機関 |
| 最終学歴の証明書 | 卒業証明書または修了証明書 | 出身校 |
| 雇用契約書の写し | 雇用条件や職務内容が確認できるもの | 所属機関 |
在留資格「日本人等の配偶者」の追加書類
| 添付書類 | 備考 | 取得先 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 発行から3ヶ月以内のもの。婚姻事実の証明と、現在の配偶者の身分事項を確認します。 | 日本人配偶者の本籍地の市区町村役場 |
| 申請人及び配偶者の収入・課税証明書 | 直近1年分の「住民税の課税証明書」と「納税証明書」が必要です。世帯の経済的安定性を証明します。 | 市区町村役場 |
| 配偶者の身元保証書 | 所定の様式に日本人配偶者が署名・捺印 | 出入国在留管理庁 Webサイト |
| 夫婦間の質問書 | 結婚に至る経緯、現在の生活状況、コミュニケーション手段などを所定の様式に記入 | 出入国在留管理庁 Webサイト |
| スナップ写真 | 夫婦で一緒に写っている写真(2~3枚程度)。交際期間や夫婦生活の継続性を証明します。 | 申請人自身(過去に撮影したもの) |
添付書類は申請書だけではわからない活動実態や生活状況を裏付ける大切な資料です。所属機関や配偶者に協力してもらい、書類を整備しましょう。
在留期間更新が不許可になる原因と対策
すでに在留している実績があるとはいえ、在留期間更新許可申請は必ず許可されるものではありません。事前に申請要件を確認してしっかり準備することが大切です。ここでは申請件数の多い就労ビザと配偶者ビザについて、不許可となる典型的なケースを紹介します。
就労のための在留資格が不許可になる例
「技術・人文知識・国際業務」など、日本で働くことを目的とした在留資格の不許可事例を紹介します。就労のために必要な在留資格は、厳密にはビザ(査証)とは異なりますが、「就労ビザ」と呼ばれることが多いです。
税金・社会保険料の未納は一発アウトの可能性も
申請する本人または所属企業が、税金(住民税、所得税など)や社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を滞納していると不許可となる可能性があります。納税は、日本の法律を守り社会的な義務を果たしているか、つまり「素行」を判断する指標です。
未納がある場合、納税証明書などにも未納であることや滞納している金額が記載されてしまいます。更新の申請前に全額を納付し、未納を解消しましょう。近年は審査が厳しくなっており、世帯主が配偶者の場合は配偶者の納税状況まで確認され、本人の在留資格更新に影響が出るケースが増えています。
会社の経営が危ない…業績悪化の影響
所属する企業の経営状況、特に業績の悪化が、在留資格の更新に影響を与える場合があります。就労のための在留資格のため、雇用が今後も安定的に継続し、給与が確実に支払われるかどうかは審査の重要なポイントです。
極端な赤字が続いている、債務超過に陥っているなど、直近の経営状況が不安定な場合、日本での活動継続が困難であると判断されるリスクがあります。このような場合、会社から経営改善計画書やあなたの雇用を維持する明確な意思を示す文書を提出してもらうなどして、あなたの活動が安定して継続できることを証明する必要があります。
入社時と仕事内容が変わったら専門分野とのミスマッチに注意
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などは、専門的な知識や技術を必要とする業務に限定されています。現在の仕事の内容が許可された在留資格の活動内容から離れている場合、更新が不許可になるリスクがあります。
たとえば、通訳として在留資格を取得した方が、実際にはほとんどの時間を単純な事務作業や接客業務を行っているケースなどです。仕事内容が変わった場合でも、専門的なスキルや知識を活かした活動であることの説明が必要です。
転職回数が多いと不利になる?
1年未満の短い期間で転職を繰り返している場合、活動の安定性・継続性に疑問をもたれる可能性があります。特に、前の会社を辞めてから次の会社に入社するまでのブランクが長い場合や、転職先の仕事内容が以前の活動内容と大きく異なる場合は要注意です。
転職回数が多い場合は「キャリアアップのため」「より専門性を高めるため」など合理的かつ前向きな理由を説明できるようにしましょう。また、現在の会社での雇用が長期にわたる安定的なものであることを証明するため、会社側からの文書を添付することも有効な対策のひとつです。
日本人の配偶者の在留資格が不許可になる例
日本人の配偶者等の在留資格の更新が許可されないのは、婚姻の実態を疑われるケース、世帯の生計が不安定なケース、税金の滞納など素行不良なケースなどがあります。それぞれ申請の際の注意点を確認しましょう。
別居で偽装結婚を疑われる
夫婦が別居していることは、「夫婦関係が破綻しているのではないか」「偽装結婚ではないか」という疑念をもたれる原因となります。
別居の事実が判明した場合は、詳細な状況の説明が求められます。夫婦の一方の単身赴任や親族の介護、入院など、別居に真っ当な理由がある場合は隠さずにはっきり伝えましょう。
申請書だけでは十分な説明ができない場合は、別居に至った経緯、現在の連絡頻度、同居再開の具体的な予定などを詳細に記した書類や、客観的な証拠(単身赴任の辞令、病院の診断書、家賃契約書など)を提出するとよいでしょう。
世帯収入が安定していない
夫婦が日本で経済的に自立した生活ができるかどうかを判断するために、世帯収入は重要な指標です。世帯収入が日本の一般的な生活水準と比較して極端に低い場合、不許可になるリスクが高まります。
ただし、単に収入が低いという理由だけで不許可になるわけではありません。収入が低い場合でも、預貯金が十分にある場合や、親族からの援助が受けられる場合はそれを証明する書類を提出しましょう。
特に、直近で配偶者が転職した、あるいは病気で一時的に収入が減少したなどの事情がある場合は、具体的な状況と今後の見込みを説明する書類が重要です。
世帯員の税金未納
日本人配偶者を含む世帯全員が納税の義務を果たしているかが厳しくチェックされます。配偶者である日本人の住民税や国民健康保険料などの未納がないかも確認しましょう。
外国人の在留資格は、日本での安定的で継続的な家族生活を前提としています。世帯としての経済的基盤や法令遵守の意識を疑われてしまうと、更新が不許可となりかねません。未納があるまま申請すると審査が極めて不利になるため、遅れがないように注意しましょう。
申請中・申請後に離婚した場合
配偶者の在留資格を取得した直後または更新申請中に夫婦関係が破綻し、離婚や離婚を前提とした別居に至った場合、偽装結婚を疑われて不許可になるリスクが高いです。
やむを得ない事情で申請後すぐに離婚が成立したり、別居したりした場合は、ビザ取得とは無関係の事情によるものであることを証明する必要があります。
この状況で日本に在留を希望する場合、別の在留資格への変更を検討する必要がありますが、許可のハードルがら高いのが実情です。一刻も早く専門家に相談し、今後の対応を慎重に検討しましょう。
不許可通知が届いたらどうする?再申請までにやるべきことリスト
万が一、在留期間更新許可申請が不許可となってしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
もし不許可通知が届いたら、指定された期間内に出入国在留管理局へ行き、不許可の理由をヒアリングしましょう。不許可の理由を知ることで、再申請で何を改善すべきかがわかります。
たとえば、不許可の理由が税金の未納であればすぐに納付し、会社の経営状況が問題であれば改善策を講じるなど、指摘された問題点を解消しましょう。そのうえで、再申請のための書類と不許可理由を解消した証拠を準備します。再申請は、前回の問題点を解決したことを強くアピールする機会となります。
不許可の場合、一般的には在留期間満了日から「特定活動」の在留資格で最大30日間の猶予期間が与えられます。不許可通知が届いた時点で専門家に相談し、再申請に向けたサポートを受けると安心です。
まとめ
在留期間更新許可申請は、日本での安定した生活を続けるための手続きです。申請書を正確に記載するだけでなく、審査官が重視するポイントを把握して十分な説明資料を添付することが重要です。
しかし、手続きに慣れていないと審査官を納得させるための資料を作成するのが難しい場合もあります。少しでも不安を感じる場合は、在留資格申請が得意な行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、在留資格更新申請についての相談を受け付けています。前回の申請時から状況が変わった方や、添付書類の作成で悩んでいる方は、ぜひお早めにご相談ください。