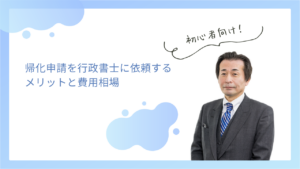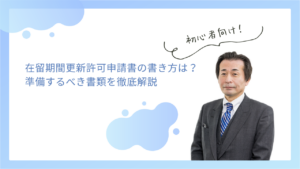在留資格「経営・管理」の取得要件は?日本での起業成功のポイント

日本で外国人の方がビジネスを営むためには、在留資格「経営・管理」が必要です。審査では、日本での事業の継続性と安定性が厳しく見られるため、要件の正しい理解と十分な準備が欠かせません。
本記事では、令和7年10月16日から施行された最新の法改正に基づく在留資格「経営・管理」の取得要件やビザ取得の流れをわかりやすく解説します。最後まで読んで、日本での起業を成功させましょう。
在留資格「経営・管理」とは?
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業を経営・管理する活動をおこなう場合に必要なビザです。具体的には、株式会社や合同会社などの法人の代表取締役や役員となる場合、または、既存事業の部長や支店長といった管理者として事業の運営に従事する場合に対象となります。
「技術・人文知識・国際業務」などの雇用される側の活動を許可する就労ビザとは異なり、経営者・管理者として事業全体を動かす活動を許可する点が大きな特徴です。
出入国在留管理庁の審査では、単に会社を設立したという形式だけでなく、日本における事業が継続的かつ安定的に運営される見込みがあるか 、法令を遵守して適正に運営されるかが厳しく確認されます。
【最新】令和7年10月16日施行|在留資格「経営・管理」の5大要件
在留資格「経営・管理」の要件は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の改正により令和7年10月16日から厳格化されました 。従来の要件と比較して、事業の規模や実現可能性を裏付けるための基準が明確化され、ビザ取得のハードルが高くなっています。
今回の改正は、日本国内で実態を伴わない事業や、不安定な経営による労働問題などを未然に防ぎ、健全な外国人起業家を歓迎するための施策といえます。ここからは、新要件をわかりやすく解説します。

資本金等の額
事業主体が法人の場合、払込済資本または出資総額が3,000万円以上であることが必須条件となりました(改正基準省令 第1号ロ) 。この基準は、事業の継続性を客観的に担保するために設定されたものであり、従来の「500万円以上」から大幅に引き上げられました。
【出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令】
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること。
事業主体が個人事業主の場合は、事業所の確保、設備投資、1年間の職員の給与など、事業を営むために投下されている総額が3,000万円以上必要です 。
申請時には、申請者の正当な資金であることや実際に事業に使われていることを証明するため、送金証明書や預金通帳の履歴など、資金の出所を明確に示す資料が必要です。
常勤職員の雇用
新しい要件として、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが義務付けられました(改正基準省令 第1号イ)。これまでの『資本金500万円 または 職員2名』という選択制は廃止され、『資本金3,000万円 かつ 職員1名』の両方を満たす必要があります。常勤職員の対象となる人材には厳格な制限があり、以下のような人が対象です。
【出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令】
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留する外国人は、この常勤職員の対象に含まれません。
つまり、外国人経営者が外国人従業員を1人雇うだけでは要件を満たせないのです。求人活動を早期に開始し、雇用契約書などの証明書類を準備する必要があります。
日本語能力
申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力(B2相当以上)」を有することが要件となりました。外国人経営者が日本人従業員や取引先と適切なコミュニケーションをとり、事業を適正に管理するための新しい基準です。
「相当程度の日本語能力」とは、具体的に以下のいずれかを満たす必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上の取得
- 日本の中長期在留者として20年以上在留していること
- 日本の大学等高等教育機関または義務教育を修了し高等学校を卒業していること
申請者自身に相当程度の日本語能力がない場合でも、常勤職員(日本人等)が日本語能力を有していれば要件を満たすことが可能です。
経歴(学歴・職歴)
申請者本人の経営・管理能力を証明するため、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 経営管理または申請に係る事業に必要な技術・知識に関する博士、修士、専門職の学位を取得していること
- 事業の経営または管理について3年以上の職歴を有すること
経営者として事業を立ち上げる場合はもちろん、支店長や部長など既存事業の管理者として申請する場合も経歴が重要です。特例として、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間も3年以上の職歴に算入されます。
職歴がなくても学位取得により要件を満たせるようになったため、優秀な若手経営人材の受け入れが可能になりました。
事業計画書の確認
提出する事業計画書について、計画の具体性・合理性・実現可能性を評価するものとして、経営の専門家による確認が義務付けられました。専門家として指定されているのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。
申請者は、専門家に事業計画書の内容を精査してもらい、実現可能であるという確認を得た文書を提出する必要があります。第三者的な視点から計画の客観的な妥当性を証明し、計画倒れのリスクを回避するために設けられた要件です。
すでに在留中の方の更新時の特例
すでに在留資格「経営・管理」で在留中の方が、改正後の許可基準にすぐに適合できない場合のために、3年間の移行措置が設けられています。
施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請をおこなう場合は、改正後の許可基準に適合していなくても、経営状況や改正基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
ただし、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合があります。猶予期間中に、赤字の解消、常勤職員の雇用、資本金の増強など、新しい基準を満たすための具体的な経営改善努力をすることが大前提です。
在留資格「経営・管理」申請のポイント
確実にビザを取得するためには、事業の継続性と高いコンプライアンス意識を示すことが大切です。具体的にどのような準備を進めるとよいのか、ポイントを解説します。
事業所の確保
改正後の厳格な要件(資本金3,000万円以上、常勤職員の雇用など)に応じた規模と機能を有する事業所を確保する必要があります。審査では、賃貸借契約書や事業所の図面・写真などから、事業専用のスペースとして適切に機能しているかが厳しくチェックされます。
原則として、申請者や家族の自宅を事業所と兼ねることは認められません。新要件では常勤職員1名以上の雇用が義務化されたため、従業員が執務するのに十分な独立した事業スペースの確保は必須です。
仮に自宅の一部を事業所とする場合、「事業の性質上、自宅でなければならない理由」を合理的な説明が必要です。また、独立したスペースが確保されていること、来客や従業員の出入りに支障がないことなどを証明する必要があるため、自宅とは別に事業所を構えることを強くおすすめします。
バーチャルオフィスについても、事業活動の実態を伴わないと判断されるリスクが高いため、避けたほうがよいでしょう。
物件を借りる場合、事業主体である法人や個人事業主の名義で正式に賃貸借契約を結び、契約書に事業用途として使用する旨が明記されていることが重要です。
経営実態の確保
在留資格「経営・管理」は、単なる資金の投下ではなく、申請者自身が事業を適切に経営・管理する活動を許可するものです。そのため、申請者本人の経営者・管理者としての活動の実態が十分に認められることが極めて重要です。
業務の大部分を外部の会社へ業務委託したり、経営判断を役員や専門家に依存したりしている場合、申請者自身が事業を経営・管理する役割を担っていないと判断されるリスクがあります。
以下のような活動を具体的におこなっていることを示せるように準備しましょう。
- 人事管理:常勤職員の採用、労働条件の決定、労務管理への関与など
- 財務管理:売上や経費の管理、銀行口座の管理、資金調達に関する意思決定など
- 事業計画の執行:営業戦略の立案と実行、取引先との折衝など
申請者自身が事業を適切に管理・執行する能力を有し、事業の意思決定をおこなっていることを証明することで、不許可のリスクを軽減できます。
公租公課の履行
特に更新申請においては、国や地方公共団体に納める税金や保険料の支払義務の履行状況が厳しく確認されます。適切な保険加入と納税は、日本社会の一員としての義務であると同時に、事業の安定性を示す指標です。
確認されるのは、以下のような公租公課の履行です。
- 労働保険:雇用保険・労災保険への加入と保険料の納付
- 社会保険:健康保険と厚生年金保険への加入と保険料の納付
- 国税:法人税、消費税、源泉所得税などの納付
- 地方税:法人住民税、事業税、固定資産税などの納付
公租公課の未納や滞納が確認された場合、たとえ事業が黒字であっても在留期間更新が不許可となる可能性が高くなります。特に社会保険の未加入は、入管の審査で指摘されやすい事項のひとつです。
会社設立直後から税理士や社会保険労務士と連携し、法令に基づいた手続きと期日内の納付を徹底しましょう。
許認可の取得
事業内容によっては、国や地方自治体からの許認可が必要です。許認可が必要な業態の例は、飲食店(飲食店営業許可)、建設業(建設業許可)、リサイクルショップ(古物商許可)、人材派遣業(労働者派遣事業許可)などがあります。
適切な許認可を得ないで営業することは違法行為であり、在留資格の不許可や取り消しに直結します。
申請予定の事業が許認可を必要とする業種かどうかは行政書士などに確認しましょう。申請書類の準備や審査に数週間から数ヶ月を要する場合があるため、会社設立や事業計画の策定と並行して、早期に着手することが重要です。
会社設立から在留資格取得までの流れ
在留資格「経営・管理」を取得するためには、出入国在留管理庁への申請に先立ち、日本での会社設立手続きを完了させる必要があります。会社設立からビザ申請・審査を経て在留資格が認められるまで、4~8ヶ月程度かかるのが一般的です。ここでは、会社設立からビザ取得までの流れを解説します。
事業計画の策定
事業計画書は、事業の実現可能性と継続性・安定性を客観的に証明するものでなければなりません。新要件では、中小企業診断士、公認会計士または税理士による確認が義務化されました。
事業計画書には以下のような内容を記載します。
- 事業内容
- 市場分析
- 競合他社や市場規模を踏まえた販売戦略
- 設立から最低3年間程度の収支予測
- 資本金3,000万円以上の資金源
- 運転資金、初期投資の資金計画
- 組織体制と採用計画
説得力があり、申請要件を満たすことがわかる内容に仕上げることが極めて重要です。専門家のアドバイスを受けながらブラッシュアップするとよいでしょう。
会社設立手続き
事業計画が固まったら、日本での会社設立手続きを進めます。日本で一般的な会社形態は株式会社または合同会社です。
まずは会社のルールブックである定款を作成します。株式会社の場合、公証役場での認証を受ける必要があります。Webで見つかるひな形をそのまま使うのではなく、行政書士などの専門家に相談して自社に合った内容に整えましょう。
続いて、資本金を発起人の個人口座に払い込みます。新要件では、3,000万円以上の資本金の払い込みが必要です。
ここまでの準備が整ったら、法務局で会社設立登記を申請します。登記完了をもって正式に法人設立となります。登記申請は添付書類が多く手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
在留資格申請に詳しい行政書士や司法書士など複数の専門家と連携して、確実に手続きをおこないましょう。
法人設立の届出と許認可取得
登記完了後は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場などに法人設立届出書や青色申告承認申請書など届出をおこないます。公租公課の履行がビザ取得の重要な要件のため、忘れずに手続きを済ませましょう。
また、前述のとおり、事業内容によっては事業を始める前に管轄の官公庁から事業許可、認可、または届出が必要です。許認可の取得には時間がかかるため、早期に手続きを進め、入管への申請時には許可証の写しを提出できるよう準備します。
出入国在留管理庁への申請
準備が整ったら、いよいよ出入国在留管理庁へ在留資格「経営・管理」の申請をおこないます。申請には、「在留資格認定証明書交付申請(日本国外から呼び寄せる場合)」と「在留資格変更許可申請(すでに日本に滞在している場合)」の2種類があります。
提出する書類の例は以下のとおりです。
- 事業計画書(専門家の確認済み文書を添付)
- 会社の登記簿謄本
- 資本金3,000万円以上の資金源を証明する資料
- 事業所の賃貸借契約書
- 常勤職員(日本人等)の雇用契約書
- 申請者(経営者・管理者)の経歴書や日本語能力を証明する資料
出入国在留管理庁は、提出された書類全体を通じて、申請された事業が安定的に継続しておこなわれるかどうかを厳しく審査します。不備があると審査に時間がかかったり、不許可になったりするリスクがあるため、行政書士などの専門家に依頼し、確実な準備をおこなうことをおすすめします。
知らないと不許可になる!新規・更新の失敗事例と注意点
経営・管理ビザの申請は、形式的な要件を満たすだけでなく、事業の実質的な安定性とコンプライアンスが入管の審査で厳しく問われるため、不許可となるケースが少なくありません。ここでは、新規申請と更新申請でよく見られる失敗事例と対策を解説します。
【新規申請】事業実態がないと判断される事例
新規申請で多い不許可の原因は「事業の実態がない」、つまり単なるビザ取得のための名ばかりの会社と判断されることです。
法改正後の新要件では資本金3,000万円が必須となりましたが、大金を投じても、ほかの面で準備が不十分では事業の実態が疑われるリスクがあります。
たとえば、バーチャルオフィスや自宅の一部を事業所としている場合、事業専用のスペースとして機能していないと判断されやすいです。常勤職員を雇用する要件が加わったことで、従業員が働くためのスペースがないと、事業実態なしとみなされる可能性が高くなります。
また、専門家が確認した事業計画書であっても、申請者自身の理解や熱意が不足していると、面談などで指摘を受ける可能性があります。事業に必要な許認可を取得せずに在留資格申請することも、事業への本気度や適法性に疑念を抱かせる要因です。
新規申請では、会社設立準備から事業計画の細部に至るまで、一貫して「日本で本気で、継続的に事業をおこなう意思と能力があること」を具体的に証明することが求められます。
【更新申請】事業の継続性が担保できない事例
更新申請の審査では、設立後の事業実績が重要視されます。事業の継続性と安定性が認められなければ不許可となる可能性もあるのです。
たとえば、複数年にわたり大幅な赤字が続いている場合、事業の安定性がないと判断されます。特に、設立時の資本金3,000万円を食いつぶすような赤字は危険です。赤字続きの場合は、原因を明確にし、具体的な経営改善計画を実行していることを示しましょう。
また、申請者への報酬が日本人と同等でない、または極端に低い場合、申請者自身が日本で安定した生活を送れていないと判断されやすくなります。申請者が日本人従業員より低い報酬しか得ていない状況は、事業の安定性を疑われるリスクがあるため要注意です。
売上がほとんどない、常勤職員を継続的に雇用できていない、事業活動が休止状態にあるといった場合は事業の継続が見込めないと判断されるでしょう。
更新申請では、前回の申請時から現在までの事業実績を客観的に示し、今後も安定して事業を継続していく見込みを示すことが許可取得の条件です。日頃から経営状況を適切に管理し、次回の更新に備えましょう。
会社運営で怠りがちなコンプライアンス違反事例
在留資格「経営・管理」の審査では、コンプライアンスが厳しく問われます。日々の会社運営の中で見落としがちなコンプライアンス違反には以下のような例があります。
- 常勤職員を雇用しているにもかかわらず、社会保険や労働保険に加入していない
- 法人として納付すべき税金に滞納がある
- 労働基準法などの労働関連法規の違反がある
- 事業に必要な許認可を取得していない、期限が切れている
- 事業内容・所在地などの変更があったにもかかわらず届出をしていない
些細なことと考えて必要な手続きを怠ると、ビザの不許可や取り消しにつながる可能性があるため注意しましょう。
長期滞在・永住権を見据えた「経営・管理」ビザ戦略
在留資格「経営・管理」は、日本でビジネスを始めるためのスタートラインです。事業を長期的に継続し、ゆくゆくは永住権の取得を目指している方もいることでしょう。将来のビザ更新や切り替えを見据えて、初回申請から計画的におこなう必要があります。
初回1年から5年への更新
経営・管理ビザの初回付与期間は一般的に1年です。この1年間の間に、事業を計画どおりに軌道に乗せ、次回の更新で3年、そして最終的に5年へと在留期間を延ばしていくことが目標となります。
1回目の更新で3年を取得するためには、事業計画が着実に実行され、事業が黒字化していることや、適切な納税が行われていること、申請者自身が日本人と同等以上の報酬を得ていることなど、事業の安定性が重要視されます。
将来的に永住権申請を考えている場合は、「最長の在留期間を有していること」を満たすために5年の在留期間が必要です。5年を取得するためには、数年間にわたる安定した事業実績と、高いコンプライアンス意識が求められます。
高度専門職ビザへの戦略的切り替え
事業が成功し、一定の要件を満たすことができれば、在留資格「高度専門職」ビザへの切り替えが永住権取得への最短ルートとなる場合があります。
高度専門職ビザには、「高度経営・管理活動」に関するカテゴリーがあり、ポイント制を採用しています。年収、学歴、職歴、日本語能力などの項目で70点以上を獲得することがビザ取得の条件です。
通常、永住権申請には10年間の日本滞在が必要ですが、高度専門職のポイントが70点以上であれば3年間、80点以上であれば1年間に短縮されます。
高度専門職のポイント要件を満たすために必要な年収の確保や日本語能力の向上を図ることが、長期的な日本での生活基盤を築く上で有効な手段です。
まとめ
令和7年10月16日より、在留資格「経営・管理」の取得要件が大幅に厳格化されました。資本金3,000万円、常勤職員の雇用、日本語能力など複数の要件を満たすのは容易ではありません。日本でビジネスを成功させるためには、最新の法令と実務を熟知した専門家のサポートが必要です。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、事業計画書の作成、会社設立、出入国在留管理庁への申請まであなたのビジネスを幅広くサポートいたします。お気軽にご相談ください。