非上場株式は生前贈与するべき?メリット・デメリットと評価方法を解説

非上場株式の生前贈与は、事業承継や相続対策において重要な選択肢のひとつです。しかし、株式の評価額や贈与税の負担、経営権の移転に伴うリスクなど、注意すべき点も少なくありません。
本記事では非上場株式は生前贈与するべきかどうか、メリット・デメリット、評価方法や活用できる制度までを整理し、トラブルを回避しながら賢く進めるための実践的な視点を解説します。
非上場株式を生前贈与するメリット|節税編
将来的に価値が上昇する見込みがある非上場株式は、生前贈与すると相続する場合に比べて節税効果が高くなる場合があります。
事業承継税制を併用することで、税務上の優遇措置が受けられるため中小企業オーナーにとっては有効な選択肢です。
将来的な株価上昇に備えられる
株価は会社の業績や市場環境に応じて変動します。業績が右肩上がりであれば、将来的に株式評価額が上昇し、相続税の負担が重くなるリスクがあります。
株価が低いうちに生前贈与することで、相続時に譲り受けた場合と比べて税負担が軽減できる場合もあるのです。
非上場株式は市場での取引がないため、評価額を普段あまり気にしない方が多いのが実際のところです。相続の段階になって初めて「こんなに評価額が高かったのか」と驚くケースも珍しくありません。
会社の業績向上や保有資産の価値上昇によって、知らない間に株価が上がっている可能性もあります。株式の評価額を把握し、早めに相続に備えることが重要です。
事業承継税制を利用できる
事業承継税制は、非上場株式を後継者に贈与した際の贈与税や相続税の納税が猶予され、一定条件を満たすと最終的に免除される制度です。後継者は多額の納税資金を用意せずに株式を引き継げます。
ただし、制度を利用するには、都道府県知事への認定申請や贈与計画の策定、雇用確保要件など複数の条件を満たす必要があります。税理士などの専門家に相談し、要件を満たすかを確認したうえで利用しましょう。
非上場株式を生前贈与するメリット|事業承継編
非上場株式の生前贈与は、節税だけでなく事業承継にも貢献します。後継者へ早期に株式を移転することで、経営権のスムーズな承継が可能です。贈与のプロセス自体が後継者育成の機会となり、事業の安定性を高めることにも直結します。
経営権をスムーズに移行する
相続による事業承継は、予期せぬトラブルを引き起こすおそれがあります。たとえば、現経営者が突然亡くなった場合、株式が複数の相続人に分散し、遺産分割協議が長引くことで会社の意思決定が停滞する可能性があります。
株式を保有する相続人が複数になると、会社の重要な経営判断(設備投資やM&Aなど)に反対され、事業の成長が阻害されるのも深刻なリスクです。
後継者を明確に定めて生前贈与で株式を計画的に移転することでリスクを回避できます。現経営者が存命中に後継者に経営権を確実に集約できるため、相続発生後も経営に支障をきたすことはありません。
後継者を育てる
事業承継は、単に株式を渡すことではありません。後継者が経営者として成長するための準備期間が必要です。
生前贈与による株式の移転と並行して、徐々に後継者の経営参加を促すことで、後継者は会社の全体像を把握し、実践的な経営課題への対応力を養うことが可能です。
たとえば、現経営者のもとで取締役として経験を積ませながら、段階的に株式を贈与し、最終的に社長の座を譲るといった計画的なステップを踏むケースがあります。
現経営者が存命のうちに経営のノウハウや企業理念を直接伝え、アドバイスを与えられる点は大きなメリットです。
会社の信用維持と安定
株式の承継は、会社の将来性を測る上で、取引先や金融機関にとって大きな関心事です。
もし、相続による突然の事業承継が発生した場合、誰が次の経営者になるのか、事業を継続していけるのかといった点が不透明になり、会社への信頼に悪影響を及ぼす可能性があります。
計画的な株式の生前贈与は、事業を継続していくという外部へのメッセージです。後継者が段階的に会社の顔として認知され、取引先や金融機関との関係を築く時間も確保できます。
融資や資金調達もスムーズになり、会社の成長に資する安定した経営基盤を構築できるでしょう。
非上場株式を生前贈与するデメリット
一方で、非上場株式の生前贈与には慎重な検討が必要です。税負担や経営権分散といったデメリットを把握し、適切な対策を講じましょう。
贈与税の負担が大きい場合がある
非上場株式の価値は、会社の業績や保有する資産によって大きく変動します。
特に、創業から長年経ち、潤沢な内部留保を積み重ねてきた会社や、都心に評価額の高い不動産を保有している会社の場合、贈与税の算定にあたって高額な価値が算出されることがあります。数千万円から数億円規模の贈与税が発生するケースも珍しくありません。
たとえば評価額が億単位の株式を後継者に一括で贈与する場合、数百万円程度の納税資金では到底足りません。贈与を実行する前に、税理士などの専門家に依頼して正確な株式評価を行い、納税資金をどのように確保するか、綿密な資金計画を立てておきましょう。
想定外の金銭負担が発生するリスク
非上場株式の生前贈与では、贈与税だけでなく、登記費用や税理士・司法書士など専門家への報酬といった費用も発生します。
また、贈与後の株価上昇により、将来の相続時や追加贈与の際に当初の想定をはるかに超える税負担が発生する可能性があるため要注意です。
キャッシュフローに余裕のない会社では、納税資金確保が経営を圧迫する可能性があるため、実行に際しては慎重な資金計画が欠かせません。
経営権分散のリスク
非上場株式を複数の子や相続人に分散して贈与した場合、会社の経営権が分散し、重要な意思決定に支障をきたすおそれがあります。
たとえば、複数名の子どもたちに株式を均等に贈与すると、意見が割れたときに取締役の選任や大規模な設備投資、新規事業への参入といった重要な経営判断を下せません。結果的に会社の成長を阻害したり、最悪の場合は経営の継続が難しくなったりするケースもあります。
株式を生前贈与する際には、誰にどの程度の議決権を承継させるかを慎重に判断することが重要です。議決権集中を目的とした種類株式の発行や、議決権を特定の相続人に集約させる信託契約の活用など、専門家と相談しながら適切なしくみを検討するとよいでしょう。
非上場株式の評価方法
非上場株式を生前贈与する際には、まず株式の評価額を算定しましょう。評価方法は法律や通達で定められており、会社の規模や業種によって適用方法が異なります。
評価額はそのまま贈与税や相続税の計算基礎となるため、専門家に相談のうえ正しく評価することが大切です。
評価額が贈与税・相続税を決定する
非上場株式は市場で自由に売買できないため、税務上の評価基準に基づいて価値を算定します。この評価額が、贈与税や相続税の計算根拠となる「財産の価値」そのものです。
たとえば、後継者に1万株を贈与する場合を考えてみましょう。1株あたりの評価額が1万円であれば、贈与財産全体の評価額は「1万円 × 1万株 = 1億円」です。もし評価方法の違いや資産変動によって1株あたり1万5,000円と評価した場合、贈与財産全体の評価額は「1万5,000円 × 1万株 = 1億5,000万円」になります。
1株あたり5,000円の評価額の差が、5,000万円の課税対象額の差となり、贈与税額が数百万円・数千万円単位で変わるケースもあります。
評価額は財務諸表の内容や業績、資産規模によって変動するため、正確かつ適切な方法で算定することが極めて重要です。
非上場株式の主な評価方法
非上場株式には大きく分けて「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の2つの評価方法があります。会社の規模や収益性によってどちらを適用するかが変わり、評価額に大きな差が出るため、正しい方法を選択しましょう。
類似業種比準方式
類似業種比準方式は、収益力を重視する評価方法です。上場している同業種の会社の株価や財務データを参考に、対象会社の「1株あたりの配当」「利益」「純資産」といった項目を比較して評価額を算出します。
会社の収益力が評価額に直接反映されやすいのが特徴です。たとえば、利益を毎年安定して出している会社や、将来の成長が見込まれる会社の場合、評価額が高くなりやすい傾向があります。
主に中小規模の同族会社で、安定した収益を上げている場合に用いられます。会社の事業価値や稼ぐ力を適正に評価できるため、実態に即した評価方法とされています。
純資産価額方式
純資産価額方式は、会社の資産価値を重視する評価方法です。会社の資産(土地、建物、現金、売掛金など)から負債(借入金、買掛金など)を差し引いた、いわゆる「純資産」の金額を基礎として評価額を算出します。この際、資産や負債は相続税評価額に置き換えられます。
会社の含み益(帳簿価額と時価の差額)が評価に大きく影響するのが特徴です。特に、帳簿上は低い価額でも時価が高い不動産を多く保有している場合、評価額が非常に高額になりやすい傾向があります。
この方式は会社の収益が不安定な場合や、赤字が続いている場合によく採用されます。また、資産管理会社など、収益性よりも資産の保有が主な事業内容である会社にも適しています。
【注意】評価額が想定外に高くなるリスク
非上場株式の評価額は、会社の財務状況や業績によって大きく変動します。特に、帳簿上は低い価額でも時価が高い不動産の含み益や、一時的な多額の利益計上があった場合、想定していた以上に高額な評価となり、結果として多額の贈与税負担が生じることがあります。
リスクを避けるためには、贈与前に財務内容を精査し、専門家と相談して最適な贈与タイミングを見極めることが重要です。
また、多額の贈与税を一度に支払うのではなく、数年に分けて段階的に贈与するといった方法も有効な対策となります。
非上場株式の生前贈与で活用できる制度と特例
非上場株式を生前贈与する際には、制度や特例を上手に活用することで税負担を軽減できます。代表的なものに暦年贈与、相続時精算課税制度、事業承継税制があります。それぞれのしくみを理解し、自社や家族の状況に適した方法を選択することが重要です。
暦年贈与
暦年贈与は、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税が非課税になる制度です。基礎控除額を利用して、毎年少しずつ株式を後継者に贈与することで、税負担を抑えつつ計画的に株式を移転できます。
特に、株式の評価額が今後大きく上昇することが見込まれる場合、価値が低いうちに贈与を始めることで節税効果が高まります。
後継者が複数いる場合、毎年110万円以内で少しずつ株式を贈与していくことで、税負担をかけずに株式を分散できる点がメリットです。会社の将来の成長を見越して、時間をかけて慎重に株式を移転したい場合にも適しています。
ただし、単に株式を渡すだけでは贈与と認められないことがあります。毎年、贈与契約書を作成し、株主名簿の書き換えを確実におこなうなど、贈与の実態を明確にすることが必須です。
また、2024年の改正により、将来の相続開始日から遡って7年以内に行われた贈与は相続税の課税対象になります。計画を立てる際には、この点も考慮が必要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されますが、将来の相続発生時に、贈与した財産の価額を相続財産に合算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税額を差し引いて精算します。
2,500万円という大きな枠を利用して、一度に多額の株式を贈与し、後継者へ速やかに経営権を集中させたい場合に適しています。
また、贈与時点の評価額で相続税が計算されるため、将来的に会社の成長で株価が大きく上昇した場合でも、贈与時点の低い評価額で税金を抑えられる点がメリットです。
2024年の税制改正により、新たに110万円の基礎控除が創設され、より利用しやすくなりました。
ただし、一度この制度を選択すると、同一の相手からの贈与については暦年贈与に戻せないため、制度の選択にあたっては税理士に相談して比較検討すると安心です。
事業承継税制(納税猶予・免除)
事業承継税制は、後継者が非上場株式を贈与または相続によって取得した際に、贈与税や相続税の納税が猶予され、最終的に免除される可能性がある制度です。
会社の評価額が高く、後継者が多額の税金を支払うことが難しい場合に有効です。納税資金の確保を待たずに経営のバトンタッチをスムーズに行い、会社の信用を維持できます。
一方、制度の適用を受けるためには、都道府県知事への認定申請、贈与計画の策定、雇用確保要件(贈与日から5年間、平均で贈与時の雇用の8割を維持するなど)といった複数の厳格な条件を満たし続ける必要があります。また、特例措置は2027年に終了する予定です。利用を検討する際は、必ず最新の制度内容を確認し、専門家に相談しましょう。
非上場株式の生前贈与手続き
非上場株式の生前贈与は、財産の移転であると同時に会社経営に直結するため、手続きを慎重に進める必要があります。現状把握から始まり、株式評価、契約書の作成、名義変更、税務申告まで複数のステップがあり、それぞれに専門的な知識が求められます。誤りがあれば税務上の否認や親族間の紛争に発展する恐れがあるため、行政書士や税理士などの専門家の関与を前提に進めることが安全です。
現状把握と専門家への相談
まず、会社の最新の財務状況(貸借対照表、損益計算書など)を正確に把握します。同時に、現在の株主構成や株式の発行状況も確認しましょう。
非上場株式の生前贈与は会社経営と密接に関わるため、初期段階で専門家の協力を仰ぐことを強くおすすめします。
株式の評価や贈与税の申告・納税に関するアドバイスは税理士、贈与契約書の作成や、株主名簿の名義変更手続きのサポートは行政書士に依頼するとよいでしょう。
親族間の意見対立が予想される場合、弁護士が法的なトラブルを未然に防ぐための相談役として適しています。早い段階で専門家に相談することで、その後の手続きが格段にスムーズになります。

非上場株式の評価と贈与計画の策定
会社の規模や業績に応じて、類似業種比準方式や純資産価額方式などを用いて、1株あたりの評価額を算定します。
そのうえで、どのような方法で贈与を進めるかを計画します。贈与する株式数やタイミングを具体的に決め、必要に応じて納税資金の準備も進めましょう。
贈与契約書の作成
口約束だけでは後々トラブルになる可能性があるため、必ず書面で贈与契約書を作成します。契約書には贈与者・受贈者の氏名や住所、贈与する株式の銘柄(会社名)、株数、贈与日などを明記しましょう。
契約書は贈与があったことを当事者間だけでなく第三者にも示せる重要な書類です。行政書士に依頼し、法的に有効な契約書を確実に作成すると安心です。

株式の名義変更手続き
贈与が完了したら、会社の株主名簿を書き換える必要があります。贈与を受けた方が、贈与契約書の控えや株券(発行している場合)を会社に提出します。会社は、提出された書類をもとに株主名簿を書き換えます。
ここまでの手続きが完了して初めて、受贈者は法的に会社の株主として認められ、議決権を行使したり、配当金を受け取ったりすることができます。
手続きを怠ると、贈与を受けた方が株主としての権利を主張できなくなる可能性があるので要注意です。
贈与税の申告・納税
贈与を受けた方は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をします。
非上場株式の評価は複雑であり、申告内容に誤りがあると税務署から指摘を受ける可能性が高いため、申告までを税理士に依頼するとよいでしょう。期限を過ぎると、加算税や延滞税が課せられるため、早めの準備が大切です。
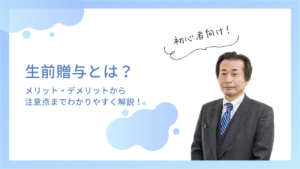
非上場株式の生前贈与でよくあるトラブルと回避策
非上場株式の贈与は、単なる財産移転にとどまらず、会社の経営権や家族関係に大きな影響を与えるため、予期せぬトラブルに発展しやすいものです。事前に想定されるリスクを把握し、適切な対策を講じておくことが重要です。
経営権の分散・親族間の対立リスク
【トラブル事例】
Aさんは長男を後継者と決めていましたが、ほかの子どもたちにも公平に株式を分け与えたいと考え、均等に贈与しました。しかし数年後、会社の経営方針を巡って長男と兄弟の間で意見が対立。大規模な設備投資を提案する長男に対し、兄弟たちはリスクを理由に反対したため設備投資は実現せず、事業の成長が阻害されてしまいました。
【回避策】
後継者を明確に定めて株式を集中して移転する計画を立てましょう。株式を複数名がもつ場合は、贈与後に経営に深くかかわっていない親族が口出ししないよう株主間契約を結び、議決権の行使や株式の譲渡について事前にルールを定めておくことも有効です。
贈与後の株価急騰による税負担増
【トラブル事例】
Bさんは息子に自社の非上場株式の一部を贈与し、残りは相続させようと考えていました。贈与当時の株価は比較的低かったものの、贈与後に会社の新規事業が大成功し、業績が急激に向上しました。Bさんが残りの株式を相続した際の評価額は贈与時と比べて大幅に上昇。想定していた税負担をはるかに超える相続税が発生し、息子は納税資金の確保に苦労しました。
【回避策】
株価が低いうちに生前贈与を始めることが重要です。多額の贈与税を一気に支払うことを避けるために、暦年贈与や相続時精算課税制度、事業承継税制の活用も有効です。
贈与を実行する前に税理士に相談し、税金対策も含めた事業承継全体の見通しをもちましょう。
遺留分をめぐるトラブルと対策
【トラブル事例】
Cさんは長女を後継者と決め、会社の株式を全て贈与しました。しかし、ほかの子には何も知らせていなかったため、Cさんの相続開始後、長女は兄弟から「遺留分が侵害されている」と訴訟を起こされました。結果として、長女は兄弟に多額の金銭を支払うことになり、親子関係も悪化してしまいました。
【回避策】
親族間の事業承継の場合、事業を継ぐ方の財産の取り分が多くなりがちです。相続人となる親族全員と十分に話し合い、合意を得ておきましょう。
配偶者、子ども、親などの相続人には最低限の取り分(遺留分)が保証されています。遺留分を侵害しないよう、不動産や現金など、株式以外の財産で相続人間の配分を調整することも検討しましょう。
遺言書を作成して遺産の分配方針を明確に示しておくことも、トラブル予防に有効です。

贈与した財産の取り戻しトラブル
【トラブル事例】
Dさんは息子を信頼し、非上場株式を全て贈与しました。しかし、息子は経営者としての資質に欠け、会社を傾かせてしまいました。Dさんは贈与した株式を取り戻したいと願いましたが、一度完了した贈与は、贈与者の意思だけでは取り消すことができず、結局会社は倒産してしまいました。
【回避策】
贈与前に、後継者の適性について慎重に見極めることが大切です。一度に全ての株式を贈与するのではなく、段階的に株式を移転し、後継者の経営者としての資質や責任感を時間をかけて確認する方法が有効です。
また、停止条件付きの贈与契約を検討するなど、有事の際に備えた契約内容を専門家と相談して盛り込むことも一つの手です。
まとめ|非上場株式の生前贈与は専門家に相談を!
非上場株式の生前贈与は、将来的な税負担の軽減やスムーズな事業承継を実現するための有効な手段です。しかし、手続きには複雑な株式の評価、専門的な制度の活用、そして親族間のトラブル回避といった多くの課題が伴います。
リスクを回避し、適切な贈与計画を立てるためには、税理士や行政書士といった専門家のサポートが欠かせません。専門家に相談することで、自社の状況に合った評価方法の選択や、暦年贈与、相続時精算課税制度、事業承継税制といった特例の最適な活用法についてアドバイスを受けられます。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、非上場株式の生前贈与についての相談を受け付けています。税理士など他士業と連携し、全ての手続きをワンストップで対応可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。









