不動産相続手続きで損しない!手順・費用・不動産の活用方法を解説

不動産相続のお悩みで多いのが「手続きが複雑そう」「税金で損したくない」というものです。不動産は高額な財産であるため、手続きを間違えると思わぬトラブルや損失につながるリスクがあります。
本記事では、不動産相続の手続きを6つのステップで解説します。手順や費用、相続した不動産の賢い活用方法までしっかり理解して、安心して手続きを進めましょう。
不動産相続手続き6つのステップ
不動産相続の手続きを知るには、遺産分割全体の流れを知る必要があります。遺産分割では、相続人全員で、亡くなった方の財産全てについて分け方を決めるためです。ここでは、遺産分割から不動産の名義変更までの手順を6つのステップに分けて解説します。
ステップ1:遺言書の確認
相続手続きを始める前に、遺言書の有無を確認しましょう。遺産の分け方を決める際、遺言書がある場合は原則として遺言書の内容が優先されるためです。
公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されています。全国どこの公証役場からでも照会が可能です。自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言の場合は、自宅の金庫などに保管されている場合があります。
自宅などで遺言書を発見した場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。封がされている場合は封を開けずに専門家に相談しましょう。
2020年からは自筆証書遺言の原本を法務局に預けられる制度も始まりました。法務局に預けていた場合は、裁判所での検認は不要です。
ステップ2:相続人・相続財産の調査と確定
相続人となる方は、亡くなった方との関係性によって決まります。これを法定相続人と言い、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることで確認できます。
相続人が配偶者と子どもなど、近しい家族のみの場合も多いのですが、思いもよらぬ相続人が見つかるケースもあります。遺産分割の話し合いは相続人全員が参加する必要があるため、手間がかかる作業ですが慎重におこないましょう。
相続財産の全容を知ることも大切です。不動産の場合、登記事項証明書や固定資産税課税明細書をもとに、不動産の所在地・面積・評価額を調査します。預貯金や株式などほかの財産もリストアップし、全体像を把握しましょう。借入金や未払い債務などのマイナスの財産も相続の対象となる点に注意し、見落としが内容に丁寧に調査しましょう。
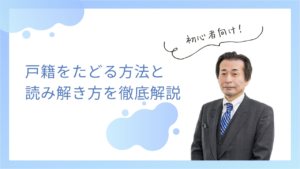

ステップ3:遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
不動産を含む相続財産は、相続人全員で分け方を話し合う「遺産分割協議」をおこない、合意する必要があります。
話し合いがまとまったら、決まった内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名押印します。遺産分割協議書は不動産の名義変更や預金の払い戻し手続きの際に必要です。
相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、その方自身が協議に参加できないため、特別代理人の専任が必要です。不動産を残すと公平な分割が難しい場合や不動産の共有を避けたい場合は、売却して現金で分割する方法や、不動産を相続した方がほかの相続人に金銭で補償する方法も有効です。
ステップ4:相続登記(不動産の名義変更)
遺産分割協議に基づき不動産を相続した場合、法務局で所有権移転登記を申請します。2024年4月から相続登記が義務化され、原則として相続の開始を知ってから3年以内に手続きをおこなわなければなりません。正当な理由なく登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産が複数ある場合は、それぞれについて登記申請が必要です。登記申請書の作成や添付書類の準備には専門知識が必要なため、司法書士に相談するとスムーズです。相続を原因とする所有権移転登記は、登記申請の際に評価額の0.4%の登録免許税がかかることも覚えておきましょう。

ステップ5:相続税の申告と納付
相続税の申告・納税期限は、原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内です。
申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)を超えるかで簡易的に判断できます。不動産が相続財産に含まれる場合は、その評価額によって相続税額が大きく左右されるため、正確な評価が必要です。
亡くなった方が生前に住んでいた家を継いで住み続ける場合など、一定の条件を満たすと「小規模宅地の特例」によって評価額が最大80%差し引かれます。不動産は財産の中でも高額になりがちですが、特例や控除を活用して税額を抑えられる可能性があります。相続税については税理士に相談するとよいでしょう。
ステップ6:相続放棄・限定承認の検討
相続財産には、プラスの財産だけでなく借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。亡くなった方の財産状況を調査した結果、借金が多い場合や債務超過が懸念される場合には、相続放棄や限定承認も検討しましょう。
相続放棄は、相続人の地位を放棄する手続きです。親族との関係が良好でない場合や、亡くなった方に借金が多い場合など、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続したくない場合に選ばれます。相続人それぞれに相続放棄を選択する権利があります。
限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法です。自宅など残したい財産がある場合に検討されます。しかし、限定承認は相続人全員でおこなう必要があり、手続きも煩雑なため、実務上は相続放棄が選ばれることが多いです。
相続放棄と限定承認はいずれも家庭裁判所での手続きが必要です。相続開始を知ってから3ヶ月が経過すると、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになるため注意しましょう。

不動産相続手続きにかかる費用と税金の種類
不動産を相続する際にかかる費用は、登録免許税や司法書士などの専門家への報酬だけではありません。不動産取得税や固定資産税など、考慮するべき費用や税金は多くあります。事前に大まかな金額を把握し、資金を確保しておくことが大切です。ここでは、不動産相続に必要な主な費用項目とその概要を解説します。
登録免許税
不動産を相続したら、登記簿の名義変更が必要です。相続が原因の所有権移転登記の場合、登記申請の際に課税される登録免許税の税率は、固定資産税評価額の0.4%です。
根拠が遺言書か遺産分割協議書かによって税率が変わることはありません。たとえば、評価額が2,000万円の土地を相続した場合、登録免許税は8万円です。
専門家への報酬
不動産相続手続きを依頼できる専門家は、専門分野によって異なります。相続人や相続財産の調査・遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士がおこないます。登記申請は司法書士の、相続税申告は税理士の専門分野です。
登記申請を代行してもらう場合の費用は、不動産1件あたり5~10万円程度が一般的です。費用は案件の複雑さや不動産の数などによって変動するため、複数の専門家から見積もりをとって比較するとよいでしょう。
相続手続きには専門知識が必要な上、膨大な時間と労力がかかります。自力で何とかしようとせず、専門家に相談することをおすすめします。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を売買や贈与で取得した際に課税される地方税です。相続による取得の場合は非課税とされています。
ただし、相続ではなく遺贈や死因贈与などの取得形態をとった場合には課税される場合があるため、不安な場合は税理士に確認しましょう。
固定資産税・都市計画税
不動産を相続すると、毎年課税される固定資産税や都市計画税の納税義務も引き継がれます。ただし、1月1日時点の所有者に対して課税されるため、新しい所有者の元に納税通知書が届くのは相続の次の年からです。
税額は不動産の評価額や所在地によって異なり、数万円から数十万円に及ぶこともあります。滞納すると延滞税が発生するため、納税通知書が届いたら早めに対応しましょう。
その他実費(戸籍謄本取得費用など)
戸籍謄本や住民票、不動産の評価証明書などの公的書類の取得には、1通あたり数百円〜数千円の手数料がかかります。相続人が複数いる場合や、被相続人の本籍地が転々としている場合は、数十通を取り寄せる必要もあり、合計で1万円以上になることも珍しくありません。申請ミスや手間を省くためにも、行政書士などに書類取得を代行してもらう方法も検討しましょう。
知っておきたい!不動産相続手続きでよくある落とし穴と回避策
不動産相続の手続きは一見単純に見えても、実際には多くの落とし穴が潜んでいます。手続きを誤ったり、準備が不十分なまま進めたりすると、思わぬトラブルに発展してしまうことも少なくありません。実際に起こりがちなトラブル事例をもとに、注意点と回避策を確認しましょう。
事例1:遺言書の見落としによるトラブル
亡くなった方が遺言書を遺していたにもかかわらず、相続人がその存在を知らずに遺産分割協議を進めてしまい、後になって遺言書が見つかってトラブルになるケースがあります。特に、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言だった場合、亡くなった方が家族に遺言の存在や保管場所を伝えていないとすぐには見つからない可能性が高いです。
すでに相続が発生している場合は、まず徹底的に遺言書を探しましょう。まずは公証役場や法務局で保管されていないか確認し、ない場合は自宅などの思い当たる場所を確認するとよいでしょう。
これからの相続に備えたい方は、遺言書の原本は公証役場や法務局で保管する方法を選び、家族にも遺言書について共有しておきましょう。
事例2:共有名義にしたことによる将来の紛争
不動産は複数名の共有名義にもできます。複数の相続人で分けるには共有名義が公平なように思えますが、将来的にトラブルを招くことがあります。売却や賃貸の判断には共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すれば実行できません。
また、共有者の一人が亡くなると、持分が次の相続人へとさらに分割され、権利関係が複雑化して有効活用できない「共有地問題」へと発展するリスクがあります。不動産はできる限り単独名義とすることが望ましく、どうしても共有にする場合は将来的な方針や管理方法を明文化しておくべきです。
公平性を重視する場合は、不動産を相続する方がほかの相続人に対して現金を支払うことで調整を図るとトラブルを回避しやすくなります。
事例3:相続税申告期限ギリギリになって慌てるケース
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。相続財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成、納税資金の準備などを10ヶ月で終えるのは、想像以上に大変です。
期限内に申告・納税できないと、延滞税などのペナルティが発生するおそれがあります。ギリギリになってから慌てなくても済むように、相続が発生したらすぐに財産の棚卸しを始め、税理士などの専門家に相談しましょう。
事例4:遠方に住む相続人との連絡が取れない
相続人の中に遠方に住んでいる人や、普段連絡を取っていない親族が含まれていると、連絡がつかずに遺産分割協議が進められないケースがあります。相続人全員の合意がない限り協議書は無効となり、登記や税務手続きも進められません。早い段階で連絡体制を整えることが重要です。
電話やメールだけでなく、内容証明郵便など正式な連絡手段を使うことで、意思確認の証拠を残すこともできます。また、話し合いが困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。相続人全員が信頼できる専門家に間に入ってもらうことで、冷静な対話がしやすくなり、円滑な協議につながります。
相続した不動産の活用方法
相続した不動産をどう扱うかによって、将来の家計や相続トラブルの有無が大きく変わってきます。活用方法には売却や賃貸などがあり、それぞれにメリット・デメリットや税務上の注意点があります。家族の生活状況や不動産の立地・状態に応じて適した方法を選ぶことが重要です。
売却する
相続した不動産を売却して現金化すると、財産として分配しやすく、不動産の維持管理の手間からも解放されます。相続税の納税資金を捻出する方法としても有効です。ただし、すぐに希望する条件で売却できるとは限らない点に注意しましょう。
また、売却して利益が出た場合は所得税が課されます。税計算のため、取得費や売却経費も含めて把握する必要があります。相続から3年以内であれば「取得費加算の特例」や、相続空き家を売却する場合の「3,000万円特別控除」などの優遇措置を活用できる可能性もあるため、事前に税理士へ相談しておくと安心です。
賃貸に出す
立地条件が良く、築年数や設備の状態が比較的良い不動産は、賃貸に出すことで収益物件として活用できます。売却せずに保有することで、安定した家賃収入が得られる点が魅力です。
将来的に自身や家族の居住用として活用する予定がある場合にも、一時的に賃貸として運用するのは有効な選択肢でしょう。
ただし、空室リスクや修繕費、固定資産税などのコストも考慮する必要があります。また、物件の管理についても、自主管理か管理会社に委託するかを事前に決めておくことが重要です。不動産管理会社や税理士と連携しながら総合的に検討しましょう。
自己利用する
相続した不動産に、相続人自身が住む、または事業所として利用する方法です。住まいとして活用すれば賃貸費用が不要となり、愛着のある実家などを守り続けられます。事業用であれば、新たな事業展開の拠点として活用できます。
ただし、固定資産税などの維持費は継続して発生し、立地や建物の老朽化によっては快適性や事業効率に課題が生じる場合もあります。家族構成やライフプランの変化にも柔軟に対応できるか考慮が必要です。
建て替え・リノベーションする
老朽化した建物を取り壊して新築したり、大規模な改修を施して現代的な機能やデザインを取り入れたりする方法です。
不動産の価値を大幅に向上させ、自己利用する際の居住性や利便性を高められます。賃貸物件として活用する場合も、高い収益性や競争力を確保しやすくなります。
多額の初期投資が必要ですが、長期的な視点で見ると資産価値の維持・向上につながり、将来の売却やさらなる活用への選択肢が広がります。
まとめ
不動産相続は「手続きが複雑で自分にできるだろうか?」「多額の税金がかかるのでは?」と心配する方も少なくありません。登記申請など不動産に特有の手続きもありますが、基本は遺産分割全体をいかにスムーズにおこなうかが重要です。
ひとりで悩まず、司法書士・行政書士・税理士などの専門家と連携して、円滑な相続手続きを目指しましょう。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続に関するご相談を受け付けています。必要に応じて税理士や司法書士などの専門家と連携して手続きが可能です。登記や相続税などお悩みが多岐にわたり相談先で悩んでいる方も、まずはお気軽にご相談ください。










